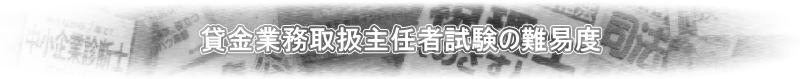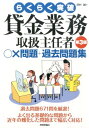その結果、日本貸金業協会の研修終了後、登録申請することで取得できた従来の制度から、国家試験に合格した者でなければ登録できない資格へと変わっています。
※ 旧主任者資格保有者に対する特例措置はないため、平成22年6月18日以降は、すべての者が国家試験に合格しなければ貸金業務取扱主任者の資格を取得することはできません。
そこで気になるのが、貸金業務取扱主任者試験の難易度です。
一般的に、国家資格は民間資格などに比べると試験の難易度は高く、合格が難しいと言われていますが、貸金業務取扱主任者試験も、国家資格に格上げされたことで取得するのが難しくなったのか・・・そのあたりを少し調べてみることにしましょう。
貸金業務取扱主任者試験は、四肢択一の完全マークシート方式を採用しているため、ビギナー受験者でも受けやすい試験です。
| 出題形式 | マークシート方式 [四肢択一] |
| 試験時間 | 2時間 |
| 問題数 | 計50問 |
この、1問2分という解答時間を短いと感じるか長いと感じるかは個人差があるかと思われますが、本試験で出題される問題のボリュームや難易度を踏まえると、極端に短いともいえず、十分落ち着いて解答することができるはずです。
貸金業務取扱主任者試験は、行政書士試験のように合格基準が前もって公開されているわけではありません。
そのため、〇〇点以上取れば絶対に合格できる!といった保証はありませんが、これまでの合格基準点を振り返ってみると、正答率は概ね60%前後で推移していることから、おそらく今後も7割(35点)以上の得点があれば、ひとまず安心といったところでしょうか。
| 実施年月 | 合格基準(計50問) | 正答率 | |
| H21.8 | 第1回 | 30問正解 | 60% |
| H21.11 | 第2回 | 30問正解 | 60% |
| H21.12 | 第3回 | 33問正解 | 66% |
| H22.2 | 第4回 | 31問正解 | 62% |
| H22.11 | 第5回 | 30問正解 | 60% |
| H23.11 | 第6回 | 27問正解 | 54% |
| H24.11 | 第7回 | 29問正解 | 58% |
| H25.11 | 第8回 | 30問正解 | 60% |
| H26.11 | 第9回 | 30問正解 | 60% |
| H27.11 | 第10回 | 31問正解 | 62% |
| H28.11 | 第11回 | 30問正解 | 60% |
貸金業務取扱主任者試験は、出題パターンがほぼ決まっていますが、これまでの過去問題を分析してみると、試験開始当初こそ本試験問題の約8割は、正誤問題(例:適切なものを1つ選べ…等)として出題されていましたが、最近は6割程度まで減少しているようです。
| ちなみに、この手の問題はケアレスミスを招きやすいといった問題点がないわけでもありませんが、貸金業務取扱主任者試験においては、どちらの解答(正しい選択肢を選ばせるのか、それとも不適切な選択肢を選ばせるのか…)を求めているのか受験者が混同しないよう、誤っている選択肢を選ばせる問題文には〝適切でない〟という本文の下にアンダーライン(下線)が引かれており非常に親切な作りとなっています。 また、本試験問題は回を重ねるごとに、若干、難化傾向にあるとも言われていますが、出題問題の大半は貸金業務に関する法令の初歩的な知識を問う問題で構成されていることから、総合的に見た試験問題の難易度はそれほど高くはありません。 したがって、過去問題をベースに市販テキストや問題集を活用しながら試験対策を行えば、独学でも十分合格を手にすることのできる程度の試験と考えられます。 |
《本試験問題の出題パターン》
|
《試験科目と出題数の目安》
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施年月 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| H21.8 | 第1回 | 46,306 | 44,708 | 31,340 | 70.1% | ----- |
| H21.11 | 第2回 | 17,780 | 16,597 | 10,818 | 65.2% | (-4.9) |
| H21.12 | 第3回 | 16,254 | 12,101 | 7,919 | 65.4% | (+0.2) |
| H22.2 | 第4回 | 9,908 | 8,867 | 5,474 | 61.7% | (-3.7) |
| H22.11 | 第5回 | 13,547 | 12,081 | 3,979 | 32.9% | (-28.8) |
| H23.11 | 第6回 | 12,300 | 10,966 | 2,393 | 21.8% | (-11.1) |
| H24.11 | 第7回 | 11,520 | 10,088 | 2,599 | 25.8% | (+4.0) |
| H25.11 | 第8回 | 11,021 | 9,571 | 2,688 | 28.1% | (+2.3) |
| H26.11 | 第9回 | 11,549 | 10,169 | 2,493 | 24.5% | (-3.6) |
| H27.11 | 第10回 | 11,585 | 10,186 | 3,178 | 31.2% | (+6.7) |
| H28.11 | 第11回 | 11,639 | 10,139 | 3,095 | 30.5% | (-0.7) |
そのため、回を重ねるごとに合格率は徐々に低下傾向にあり、第5回に突入するとガクッと急激に落ち込んでいます(しかし、近年はだいぶ落ち着いた感がある…)。
※ 試験開始当初のハードルが低い理由 … 法律上、貸金業を営む者は、営業所や事務所毎に貸金業務取扱主任者を所定数配置することが義務付けられているため、業務上、混乱を招かないためにも、有資格者が一定数に達するまで合格しやすい体制にしていることが多い。
有資格者が一定数に達した場合には、試験問題の難易度が上がることが多いので、貸金業務取扱主任者の資格取得を考えている者は、あまり先延ばしするよりも、できるだけ早期に試験合格を目指した方が賢明かもしれません。
| 過去問題:第6回試験 問2より抜粋 貸金業者が貸金業の登録を更新する場合等に関する次のa.dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a.貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日までに当該登録の更新を申請しなければならない。 b.貸金業者向けの総合的な監督指針では、貸金業法第6条第1項第15号に規定する「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」であるかどうかの審査に当たっては、登録申請書及び同添付書類をもとに、ヒアリング及び実地調査等により検証し、特に申請者の社内規則等は貸金業協会の自主規制規則と同等の社内規則等となっているか等の点に留意するものとされている。 c.貸金業の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 d.内閣総理大臣の貸金業の登録を受けた貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとする場合、政令の定めるところにより15万円の手数料を納めなければならない。 ① ab ② ac ③ acd ④ bcd |