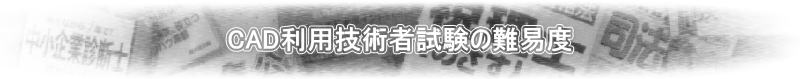ところが、この手のIT関連資格試験は、受験料が高額であることも珍しくはなく、CAD利用技術者試験においても、バカ高いとは言わないまでも、結構な受験料を覚悟しなければなりません。
となれば、受験料を無駄にしないためにも、できることなら一発合格を目指したいところです。
そこで、これまでの試験データや近年の出題内容を分析し、本試験で出題されるCAD利用技術者試験の難易度がいったいどの程度なのか、そのレベルをある程度客観的に把握しておきましょう。
※ 3次元CAD利用技術者試験の難易度については別ページ(3次元CAD編)で分析します。
| 区分 | 求められるレベル・合格者像 | 受験料(税抜き) | ||
| 基礎 | 設計や製図、CADシステムの販売等に従事する者 | 4,000円 | 併願受験 --- 3D --- 1級・2級 …… 20,000円 準1級・2級 … 15,000円 |
|
| 2次元 (2D) |
1級 | 概ね1年以上の就学・就業経験者 | 15,000円 | |
| 2級 | 概ね半年以上の就学・就業経験者 | 5,500円 | ||
| 3次元 (3D) |
1級 | 実践的なパーツ作成およびアセンブリができること | 15,000円 | |
| 準1級 | 基本的なパーツ作成ができること | 10,000円 | ||
| 2級 | 3次元CADシステムを取り扱う上で必要な基礎知識、運用知識、活用手法等を習得していること | 7,000円 | ||
具体的には、CADに関する基本的な機能や専門用語を理解しているかといった問題が中心で、特にこれといって難易度の高い高度な問題は出題されません。
| 実施年度 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| H23 | 856 | 747 | 462 | 61.8% |
| H24 | 815 | 739 | 498 | 67.3% |
| H25 | 779 | 730 | 521 | 71.3% |
| H26 | 899 | 831 | 502 | 60.4% |
| H27 | 1,085 | 961 | 506 | 52.7% |
ちなみに、基礎試験の試験結果を分析してみると、その合格率は概ね60~70%台と、非常に高い水準で推移しています(近年の下降傾向が少し気にはなりますが…)。
通常、合格率が60~70%前後で推移するような資格試験においては、試験の難易度がどうこうの問題ではありません。
つまり、基礎試験で不合格になるような人は、試験対策をほとんどしていないような、単なる勉強不足が理由と考えられます。
各級の詳細については下記にまとめておきますが、試験方法は大きく2つ〝筆記〟と〝実技〟とに分かれます。
筆記試験に関しては、1級・2級ともにマークシート方式なので、初心者にも受けやすい面がありますが、過去の出題例を比較してみると、2級試験がCADに関する基本的な知識の確認問題が中心であるのに対し、上位級にあたる1級試験では、より専門的な知識が受験者に求められていることから、非常に難易度が高く感じられるかもしれません。
《過去の出題例 1級:機械》
|
《過去の出題例 2級》
|
| 出題される問題も、公式テキストに書かれていないかなりかなり難易度の高い高度な問題が出されることも珍しくはないので、満点を狙うのは難しいかもしれません。 しかし、必ずしも満点を目指す必要のない試験なので、本試験では難問に時間をかけるよりも、解ける問題から解いていき、合格基準を超える得点を上げることを目標とした方がよさそうです。 CAD利用技術者試験では、下記のような合格基準が設けられていますが、ここで注目すべきは、各分野(あるいは、筆記試験と実技試験)ごとに合格ラインが設けられている点です。 |
- 1級試験 … 筆記試験・実技試験が各5割以上、および総合が7割以上
- 2級試験 … CADシステム分野・製図分野が各5割以上、および総合が7割以上
一方、1級試験においては、筆記試験と実技試験ともに5割以上の正解率が合格条件の一つぶなっていることから、本試験におけるウェートは実技試験の方が高い(出題比率 … 筆記:実技 = 25%:75%)とはいえ、筆記試験もある程度しっかりと対策をしておかなければ、思わぬ形で足元を救われかねません。
| \ | 建築 | 機械 | トレース | |
| 出題範囲 | ■実技試験 RC造:平面図、断面図、立面図、矩計図、展開図 木造:平面図、断面図、立面図、展開図 ■筆記試験 建築製図の基礎知識 … 建築業務の基本知識、建築製図、建築の主な構造、建築の主な材料と部材、モデュール、建築業務と建築図面の役割 建築生産の電子情報 … 建築CALS/EC、建築生産業務の電子情報化、建築CAD図面作成要領(案)、コンピュータによるシミュレーション |
■実技試験 機構部品の作図 … リンク機構、カム機構 投影図からの作図 … 第三角法 適切な数値(カタログ、要目表など)からの作図 … 機械要素部品 ■筆記試験 機械製図の知識 … 機械製図の基本、材料、公差とはめあい、幾何公差、表面性状、加工方法、機械要素 |
■実技試験 編集・レイヤ設定能力 … 図形の編集、コマンド機能、レイヤ設定 トレース能力 … 図面のトレース 投影能力 … 投影関係と形状理解 ※ 出題される分野の専門知識は必要ないが、図記号・線種などの知識は必要。 ■筆記試験 製図の知識 … 図面の名称、線の種類と用途、寸法補助記号、図記号(建築、機械、土木、電気) |
|
| 出題比率 |
|
|||
| 試験時間 | 80分(保存時間を含む) | |||
| 合格基準 | 実技試験・筆記試験が各5割以上、および総合が7割以上 | |||
| 出題範囲 | ■CADシステム分野 CADシステムの概要と機能、CADシステムの基本機能、CADの作図データ、CADシステムとハードウェア、CADシステムとソフトウェア、ネットワークの知識、情報セキュリティと知的財産、CADシステムの運用・管理と課題、3次元CADの基礎知識 ■製図分野 製図一般、製図の原理と表現方法、製図における図形の表現方法 |
| 出題比率 | 計60問 マークシート形式(多肢選択方式) ■ CADシステム分野 …… 60% ■ 製図分野 ……………… 40% |
| 試験時間 | 60分 |
| 合格基準 | CADシステム分野・製図分野が各5割以上、および総合が7割以上 |
《2次元CAD利用技術者試験2級》
|
《2次元CAD利用技術者試験1級》
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD利用技術者試験は、受験者を落とすための試験ではなく、あくまでCADに関する一定のスキルが身についているかどうかを証明するための試験ですが、絶対評価試験としての性格を持っていることから、本試験問題の難易度によって受験者の合否が左右されやすいといった特徴もみられます。
※ 絶対評価試験 … 規定の合格基準(例:100点満点中70点以上)さえ満たしていれば、原則、合格する試験制度。受験者同士で競い合うことがないため、試験問題の難易度により、合格率が大きく変動しやすいのが特徴(試験問題が易しいと大量に合格者数が出るが、試験問題の難易度が高い時期に受験してしまうと合格者数は激減してしまう…いわば運的な要素も強い)。
しかし、各試験ともに基本的には日経BP社より販売されている公式ガイドブックに準拠した問題が出題されることから、受験者は必ず最新の公式ガイドブックを入手し、本書を併用しながら試験対策を行うことで、独学でも十分合格は狙えるはずです。