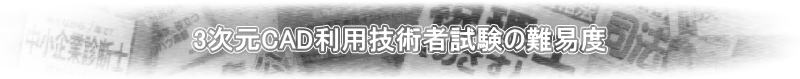3次元CAD利用技術者試験は、2次元よりも難易度が高いとされていますが、これまで2D(縦・横)では表現できなかった奥行きを加えたことで、より複雑な立体図面が作成できるとして、今後は3次元CADへの依存が強くなると言われています(とはいえ、受験者数はそれほど増えていないので、試験に関して言えば、必ずしも注目されているとは限りませんが…)。
そこで、これまでの試験データを基に、3次元CAD利用技術者試験の難易度を少し客観的に分析してみたいと思います。
具体的には、1級と準1級が実技試験、2級は筆記試験で合否判定を行います。
各級の詳細については、下記に示した試験概要を参考にしてもらうとして、ここでは過去の出題例や出題パターンを基に、3次元CAD利用技術者試験の難易度について少し分析してみましょう。
| \ | 1級 | 準1級 | 2級 |
| レベル | 実践的なパーツ作成およびアセンブリができること | 基本的なパーツ作成ができること | 3次元CADシステムを取り扱う上で必要な基礎知識、運用知識、活用手法等を習得していること |
| 試験方法 | 3次元CADシステムを利用したモデリング、アセンブリ | 3次元CADシステムを利用したモデリング | マークシート方式による多肢選択方式、および真偽方式 |
| 試験時間 | 120分 | 120分 | 60分 |
| 出題形式 | マークシート形式 (多肢選択式) |
マークシート形式 (多肢選択式) |
マークシート形式 (多肢選択式/真偽式) |
| 合格基準 | 各分野で5割以上、および総合が7割以上の正解 | ||
| 受験料 (税抜き) |
15,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
| 併願受験可 … 1級・2級併願(20,000円)/ 準1級・2級併願(15,000円) | |||
また、2級は多肢選択方式の筆記試験として出題されるため、知識さえしっかりと理解していれば、複数の選択肢の中から選ぶだけなので、解答欄がまったく埋められないということもありません。
ちなみに、2級試験の問題は、すべて日経BP社より販売されている『3次元公式ガイドブック』に準拠して出題されるので、この公式ガイドブックさえ理解しておけば、難なく合格ラインに届く実力が身に付く(つまり、どれだけガイドブックを理解しているかがポイント!)こと、問題数は多いものの、各設問が短く、3択や正誤問題(〇か×かの2択のようなもの)で構成されていることから、ビギナー受験者にも受けやすい内容になっているのが特徴です。
なお、参考までに平成25年度の試験ガイダンスによると、2級試験の内訳は【2択問題:16問、3択問題:16問、正誤問題(4択):16問、穴埋め問題(9択):12問となっており、出題問題数60問に対し、試験時間は60分間となります。
| ※補足:平成25年度より、3次元CAD利用技術者試験2級は、試験時間や設問数、出題形式が変更されています。出題形式の詳細については、最新の公式ガイドブックをご覧ください。 そのため、計算上1問あたりに割ける時間は1分となるので、本試験会場ではあまりゆっくりと時間をかけて問題を解いているわけにはいきません。 この点が、やや受験者を不安にさせる要素と言えそうです。 したがって、2級試験に関しては、問題の難易度どうこうよりも、つまらないケアレスミスをしないよう集中力を切らさず、いかにスピーディーに問題を解いていくかがポイントになってきそうです。 |
| 過去の出題例:2級 問:アセンブリの特徴として適切なものは、次のうちどれか。 《解答群》 (1)パーツやサブアセンブリがもつ要素の種類は、ソリッドもしくはサーフェスに限られている。 (2)アセンブリは、同一階層に置く場合に限り、パーツをコピーして複数個含むことができる。 (3)アセンブリは、モデルの形状に影響することなく、パーツを組み立てた状態の断面を表示することができる。 |
こちらは、筆記試験ではなく実技試験で合否判定を行いますが、いったいどういった内容の実技試験が行われるのか少なからず気になるのではないでしょうか。
簡単に説明すると、各分野で出題される問題の指示通りにモデリングを行い、数値を計測した後、設問で求められている数値に最も近い選択肢を選んで解答するという形での出題が中心となります。
したがって、2級試験とは異なり、各設問の意図をしっかりと読み取り、モデリングする技術が求められますが、あまりもたついていると時間切れになってしまうので、2級と比較するならば、正確さと迅速さが要求される明らかに難易度の高い試験です。
| 1級 |
| CADリテラシー問題、空間把握能力問題 文章によるモデリング手順に従い、部品を作成する問題。第三者との口頭によるやり取りや手描き図面情報の伝達をイメージし、的確にコマンドを使用できるかを問う。投影図、展開図より、部品を作成する問題。空間形状が把握できているかを問う。 部品組立て能力問題 部品を作成し、それらを組み立てる問題。正しく部品を組み立てられるかを問う。 2次元図面からの作図能力問題 2次元図面より、機械部品を作成する問題。実務の基本的な能力を総合的に問う。 |
| 準1級 |
| CADリテラシー問題、空間把握能力問題 文章によるモデリング手順に従い、部品を作成する問題。第三者との口頭によるやり取りや手描き図面情報の伝達をイメージし、的確にコマンドを使用できるかを問う。投影図、展開図より、部品を作成する問題。空間形状が把握できているかを問う。 2次元図面からの作図能力問題 2次元図面より、機械部品を作成する問題。実務の基本的な能力を総合的に問う。 |
| 2級 |
| 3次元CADの概念 3次元CADとは、3次元CADの必要性、3次元CADの歴史、3次元モデルのデータ構造、表示技術、3次元モデルの構成 3次元CADの機能と実用的モデリング手法 3次元CADによる設計、モデリング機能、実用化の事例、複合化したコマンド、検査・計測・解析の方法、パラメトリックモデリング、アセンブリモデリング、実用上の注意点 3次元CADデータの管理と周辺知識 PDM、プロジェクト管理、コンピュータシステムの構成、CADとネットワーク知識、情報セキュリティ 3次元CADデータの活用 CAE、CAM、CAT、CG、RP、DMU、コラボレーション、3次元CADデータの応用例 |
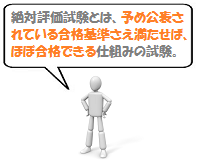 3次元CAD利用技術者試験では、下記に示すような合格基準が設けられていることから、絶対評価試験であることがわかりますが、ここで注目したいのは、この試験は総合点だけで合否判定するのではない!ということです。
3次元CAD利用技術者試験では、下記に示すような合格基準が設けられていることから、絶対評価試験であることがわかりますが、ここで注目したいのは、この試験は総合点だけで合否判定するのではない!ということです。つまり、各分野ごとに足切りラインがあるため、各分野バランスよく勉強し、本試験である程度、得点を稼がなければなりません。
したがって、極端な苦手分野がある受験者にとっては、思った以上に難易度が高く感じられる試験といえるでしょう。
| 合格基準:各分野で5割以上、および総合7割以上の正解を合格ラインとする |
| 《3次元CAD利用技術者試験》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このデータを見る限りでは、本試験問題の難易度が徐々に上がっているのではないかと推測されがちですが、必ずしも問題のレベルが上がったとは言い切れないので、今後の推移に注目しましょう。 一方、実技試験が実施される1級・準1級試験になると、2級よりも合格率は平均して低い水準で推移しています。 準1級以上の試験ともなると、受験者数が大幅に減っており、おそらく興味本位で受験される方も少ないはずです(受験料も馬鹿にならないので…)。 そのため、合格率の数値だけ見ると、概ね40~50%前後で推移しているので、結構、合格しやすいのでないかと思えなくもありませんが、受験者層はビギナー受験者というよりも、それなりにスキルをもった方が本試験に臨んでいる(準1級以上には、受験資格(2級合格者)がある)ので、見た目以上に難易度の高い試験であると理解しておいた方がよさそうです。 |