しかし、作業主任者は伝熱面積の大きさに応じてボイラー取扱主任者を選任しなければならないため、一級ボイラー技士は、下記に示すような点で他の等級と異なってきます。
| 特級ボイラー技士 | 全ての規模のボイラー取扱作業主任者となることができる |
| 1級ボイラー技士 | 伝熱面積の合計が25㎡以上~500㎡未満のボイラー取扱作業主任者となることができる |
| 2級ボイラー技士 | 伝熱面積の合計が25㎡未満のボイラー取扱作業主任者となることができる |

※ 平成16年度の制度改正により、受験資格が緩和され、二級ボイラー技士免許を受けている者は免許試験に限って、いつでも受験可能(ただし、免許申請には実務経験が必要!)。
| 試験科目 | 問題数 | 試験時間 | 試験形式 | |
| 午前 | ボイラーの構造に関する知識 | 10問(100点満点) | 2時間 [10:00~12:00] |
マークシート方式 [五肢択一] |
| ボイラーの取扱いに関する知識 | 10問(100点満点) | |||
| 午後 | 燃料及び燃焼に関する知識 | 10問(100点満点) | 2時間 [13:30~15:30] |
|
| 関係法令 | 10問(100点満点) | |||
| 資格区分 | 国家試験 |
| 受験資格 | あり [上記、受験資格参照] |
| 試験日 | 5~7回程度 / 年 |
| 受験手数料 | 6,800円 |
| 試験時間 | 4時間(午前:2時間 / 午後:2時間) |
| 試験形式 | マークシート方式 [五肢択一] |
| 試験科目 | Ⅰ.ボイラーの構造に関する知識 Ⅱ.ボイラーの取扱いに関する知識 Ⅲ.燃料及び燃焼に関する知識 Ⅳ.関係法令 |
| 合格基準 | 4科目の合計点が60%以上、かつ、科目ごとの得点が40%以上の2条件で合否を判定 |
| 合格率 | 受験者:6,094人 / 合格者:3,534人 / 合格率:58.0%(H27年度) |
| 主催団体 | 本部: 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1千代田ファーストビル東館9階 TEL:03-5275-1088 |
この点を踏まえると、一般的に難しいとされている国家試験の中では、比較的、高い水準で推移しているといえるでしょう。
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| H23 | 7,843 | 4,414 | 56.3% |
| H24 | 7,633 | 4,315 | 56.5% |
| H25 | 7,342 | 4,038 | 55.0% |
| H26 | 6,666 | 3,876 | 58.1% |
| H27 | 6,094 | 3,534 | 58.0% |
| 一級ボイラー技士試験対策向けの市販テキストや問題集自体の数が少ないため、他社よりも、より質の高い教材を作ろうといった意気込みが作り手側から感じられず、試験問題とマッチしていない不安の残る教材が目立つ... |
また、独学ではちょっと…と不安のある受験者は、各支部で開催している一級ボイラー技士免許試験に備えての講習会等に参加するのも一法かもしれません。
|
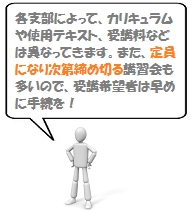 |
本試験会場では時間配分を意識しながら解くこと!
一級ボイラー技士試験の試験時間は4時間なので、計算上、1問当たりに掛けられる時間は〝6分〟(もちろん、見直し時間や問題の内容によって解答時間は変わってきますが…)ジャストとなります。
| しかし、見直し時間等を考慮すると、1問当たり〝5分30秒〟程度(もちろん、問題の内容によって解答に要する時間は前後しますが…)での解答が理想的かもしれません。 この持ち時間を長いとみるか短いとみるかは人それぞれですが、正誤問題(正しいものはどれか?誤っているものはどれか?)を中心とした、この手のマークシート形式試験は、終了時間が迫っているのに、まだまだ解かなければならない問題が残っていると、つまらないミスをするものです。 したがって、本試験会場では、問題を解くペースを意識しながら、難問と思われる設問や時間がかかりそうだなと感じた問題は後回しにするなどの工夫が必要です。 また、ケアレスミスのリスクを減らす意味でも、問題番号の余白に正しいものを選び出す場合は「〇」誤っているものを選び出す場合は「×」といったようにマークしておくのもこの手の解答方法には有効なテクニックのひとつです。 |
| (過去問題:例) ボイラーの附属品及び付属装置に関し、次のうち誤っているものはどれか。 (1)脱気器は、給水中の酸素など溶存気体を取り除くために、給水ポンプの吸込み側に設ける。 (2)給水加熱器には、加熱蒸気と給水とが混合される混合式と加熱管を隔てて給水を加熱する熱交換式があり、後者が広く用いられている。 (3)沸水防止管(アンチプライミングパイプ)は、多数の穴のあいたパイプで、上部から蒸気を取り入れて水滴を下部の穴から流すようにしたものである。 (4)スクラバは、波板を重ねたものに蒸気を通し水滴を波板に衝突させて分離するもので、気水分離器の一種である。 (5)変圧式スチームアキュムレータは、送気系統中に設けられ、余分の蒸気を加熱蒸気の状態で蓄えるものである。 |

