ボイラー技士の資格を取得するには、この主催団体が実施しているボイラー技士試験に合格しなければなりませんが、試験は取り扱うことのできるボイラーの伝熱面積の大きさによって3等級(特級/1級/2級)に区分されています。
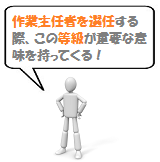
※ ただし、どの級の免許であっても、すべてのボイラーを取扱うことができる。
たとえ、どの級の免許であっても、すべてのボイラーを取り扱うことができるのであれば、ボイラー技士試験に等級を設ける必要などないのでは…?と思った方もいるはずですが、ボイラー技士の資格に等級が設けられているのは次のような理由からです。
| 事業者は、取扱うボイラーの規模によって、ボイラー技士の中から作業主任者を選任しなければならない 【労働安全衛生法 第14条】
|
そのため、作業主任者を選任する際には等級が重要な意味を持ってくると言うわけです。
| 特級ボイラー技士 | 全ての規模のボイラー取扱作業主任者となることができる |
| 1級ボイラー技士 | 伝熱面積の合計が25㎡以上~500㎡未満のボイラー取扱作業主任者となることができる |
| 2級ボイラー技士 | 伝熱面積の合計が25㎡未満のボイラー取扱作業主任者となることができる |
| 資格区分 | 国家試験 |
| 受験資格 | あり [下記、受験資格参照] |
| 試験日 | 特級 ………… 1回 / 年《10月》 1級 ………… 1回程度 / 2ヵ月 [地域によって異なる] 2級 ………… 1~2回 / 月 [地域によって異なる] |
| 受験手数料 | 各試験:6,800円 |
| 試験時間 | 特級 ………… 4時間 ※ 科目免除者は1科目1時間減 1級 ………… 4時間 2級 ………… 3時間 |
| 試験形式 | 特級 ………… マークシート方式 [五肢択一]と一部記述式問題を採用 1級 ………… マークシート方式 [五肢択一] 2級 ………… マークシート方式 [五肢択一] |
| 試験科目 | Ⅰ.ボイラーの構造に関する知識 Ⅱ.ボイラーの取扱いに関する知識 Ⅲ.燃料及び燃焼に関する知識 Ⅳ.関係法令 |
| 免除制度 | 特級のみ科目合格有り《2年間有効》 |
| 合格基準 | 科目ごとの得点が40%以上で、かつ、合計点が60%以上であること |
| 合格率 [H27年度] |
特級 ………… 受験者:574人 / 合格者:137人 / 合格率:23.9% 1級 ………… 受験者:6,094人 / 合格者:3,534人 / 合格率:58.0% 2級 ………… 受験者:28,060人 / 合格者:16,935人 / 合格率:60.4% |
| 主催団体 | 本部:公財財団法人 安全衛生技術試験協会 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1千代田ファーストビル東館9階 TEL:03-5275-1088 |
冒頭でも触れたように、ボイラー技士の資格を得るには、(公財)安全衛生技術試験協会が実施しているボイラー技士試験を受け、合格しなければなりませんが、ボイラー技士試験は誰でも自由に受験することができるわけではありません。 つまり、一定の受験資格がいるということです。 2級ボイラー試験については、平成24年4月1日以降、受験資格が廃止されましたが、ボイラー技士試験の受験資格は等級ごとに異なってくるので、受験者は必ず各自で該当する等級の受験資格を確認するようにしてください。 |
| 特級 | ① 一級ボイラー技士の免許を受けた者 ② 学校教育法による大学、高等専門学校でボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後2年以上の実地修習者 ③ 熱管理士免状(エネルギー管理士(熱)免状も該当)を受けた者で、2年以上の実地修習者 ④ 海技士(機関1,2級)免許を有する者 ⑤ ボイラー・タービン主任技術者(1種,2種)の免状を有する者で、伝熱面積の合計が500㎡以上のボイラーの取扱い経験者 |
| 1級 | ① 二級ボイラー技士の免許を受けた者 ② 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校等でボイラーに関する学科を修め卒業した者で、その後1年以上の実地修習者 ③ 熱管理士免状(エネルギー管理士(熱)免状も該当)を有する者で、1年以上の実地修習者 ④ 海技士(機関3級以上)免許を受けた者 ⑤ ボイラー・タービン主任技術者(1種,2種)の免状を有する者で、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーの取扱い経験者 ⑥ 保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格したもので、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーの取扱い経験者 |
| 2級 | 平成24年4月1日以降は不要(ただし、本人確認証明書の添付は必要) ----- 参考:従来の受験資格 ----- ① 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校等においてボイラーに関する学科を修め3ヶ月以上の実地修習者 ② 6ヶ月以上ボイラーの取扱いの実地修習者 ③ 都道府県労働局長が指定するボイラー実技講習(20時間)を修了者 ④ 都道府県労働局長又は登録教習機関が行ったボイラー取扱技能講習を修了し、4ヶ月以上小規模ボイラーを取扱った経験者 ⑤ 熱管理士免状(エネルギー管理士(熱)免状も該当)を有する者で、1年以上の実地修習を経た者 ⑥ 海技士(機関3級以上)免許を受けた者 ⑦ 海技士(機関4,5級)の免許を有する者で、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーの取扱経験者 ⑧ ボイラー・タービン主任技術者(1種,2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーの取扱い経験者 ⑨ 保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格したもので、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験者 ⑩ 鉱山において伝熱面積の合計が25m2以上のボイラーを取り扱った経験者。但しゲージ圧力が0.4MPa以上の蒸気ボイラー又はゲージ圧力0.4MPa以上の温水ボイラーに限る。 |
ボイラーは、爆発や破裂などの危険性も高いため、ビルやマンション、学校や工場、病院等に設置されているボイラーを取り扱うには、ボイラー技士試験を受け、免許申請手続きを行った有資格者でなければなりません。
そのため、ボイラー技士の資格は需要が高く安定した収入が望める!あるいは、ボイラーの点検・管理は身体的負担も少ないため、中高年者が定年後の収入源として活かせる資格である!といった話もよく聞きますが、近年は次のような背景により、ボイラー技士の需要は減ってきている(つまり、重宝されなくなった)との指摘もみられます。
資格試験に向けた勉強法は大きく2つ〝独学〟と〝専門講座〟に分けることができますが、ボイラーのような専門的な設備を取り扱う資格試験ともなると、初学者にとっては独学ではちょっと不安といった気持ちを抱いてしまう受験者も少なくないようです。
しかし、下記データからも分かるように、ボイラー技士の中でも特に人気の高い2級ボイラー技士試験を見てみると、ここ数年における2級ボイラー技士試験の合格率は、概ね50~60%前後と比較的高い水準で推移していること、また、試験形式は五肢択一のマークシート方式であること、さらに、これまでの試験問題を振り返ってみても、毎年、出題パターンがほぼ決まっていることなどから、独学でも十分合格が狙える試験です。
特級ボイラー
|
1級ボイラー
|
2級ボイラー
|
| したがって、自己管理さえしっかりとできる人であれば、市販テキストを通読した後、過去問を中心に問題を解き、分からなかった箇所はテキストを読み返すといったオーソドックスな反復学習法を行えば、独学でも十分合格は可能かと思われます。 ただし、ボイラー技士試験は、1科目でも40%を切る試験科目があると、総合点が60%以上であっても不合格となってしまう合格基準が設けられているので、極端な苦手科目は作ってはならない!といった注意点があります。 そのため、すべての試験科目をみな同じように勉強するよりも、自分にとっての得意科目と不得意科目を見極め、試験科目ごとに充てる学習時間を調節しながら、バランスのよい学習を心がけなくてはいけないので、試験対策に不安のある方は、専門講座を活用しながら効率よく試験対策を行うのも一法かもしれません。 |


