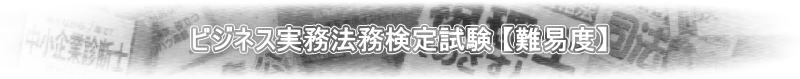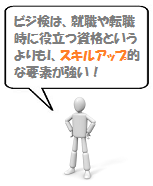 ビジネス実務法務検定試験は、受験者の能力(法知識の習得度)に応じて1~3級に区分されていますが、上位級ほど試験の難易度は高く、合格するのが厳しくなってきます。
ビジネス実務法務検定試験は、受験者の能力(法知識の習得度)に応じて1~3級に区分されていますが、上位級ほど試験の難易度は高く、合格するのが厳しくなってきます。※ ビジネス実務法務検定には、準1級の認定制度もありますが、この制度は、あくまで1級不合格者の得点上位者に付与する認定制度であって、受験者が準1級の試験区分に申込むことはできません。
そこで、ビジネス実務法務検定における各等級の難易度がいったいどの程度なのか・・・
これまでの受験者データを基に少し分析してみましょう。
ここ数年の受検結果を振り返ってみると、上位級ほど合格率が低くなる傾向にあり、ビジネス実務法務検定1級試験の合格率に至っては、10%前後という低水準で推移していることから、一筋縄ではいかない非常に難易度の高い検定試験であることが伺えます。
一方、3級試験の合格率は、非常に高い水準で推移していますが、合格率が60~70%に上るような、この手の検定試験においては、よほど勉強不足の受検者でもなければ不合格にはならないため、基礎知識の確認レベルの問題が中心に出題されているようです。
| 実施年度 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||
| 受検者 | 合格者 | 合格率 | 受検者 | 合格者 | 合格率 | 受検者 | 合格者 | 合格率 | ||
| H24 | 第31回(7月) | --- なし --- | 5,887 | 2,165 | 36.8% | 8,705 | 6,146 | 70.6% | ||
| 第32回(12月) | 691 | 75 | 10.9% | 7,783 | 3,454 | 44.4% | 10,090 | 7,914 | 78.4% | |
| H25 | 第33回(7月) | --- なし --- | 6,348 | 3,458 | 54.5% | 9,137 | 7,112 | 77.8% | ||
| 第34回(12月) | 645 | 69 | 10.7% | 7,825 | 3,011 | 38.5% | 10,160 | 8,087 | 79.6% | |
| H26 | 第35回(7月) | --- なし --- | 6,498 | 2,824 | 43.5% | 8,318 | 5,620 | 67.6% | ||
| 第36回(12月) | 635 | 64 | 10.1% | 7,887 | 2,507 | 31.8% | 10,699 | 7,273 | 68.0% | |
| H27 | 第37回(7月) | --- なし --- | 6,504 | 1,357 | 20.9% | 9,354 | 6,944 | 74.2% | ||
| 第38回(12月) | 569 | 66 | 11.6% | 8,788 | 2,160 | 24.6% | 11,437 | 8,482 | 74.2% | |
| H28 | 第39回(7月) | --- なし --- | 6,813 | 2,811 | 41.3% | 9,251 | 6,806 | 73.6% | ||
| 第40回(12月) | 8,987 | 2,245 | 25.0% | 11,523 | 7,303 | 63.4% | ||||
ビジネス実務法務検定試験受験者を業種別に分類した資料として、下記のようなデータ【東京商工会議所HPより】があります。
このデータによると、いずれの級も学生より社会人受験者の方が圧倒的に多いことが伺えますが、さらに注目すると、上位級ほど学生の受験者が減っていることに気付きます。
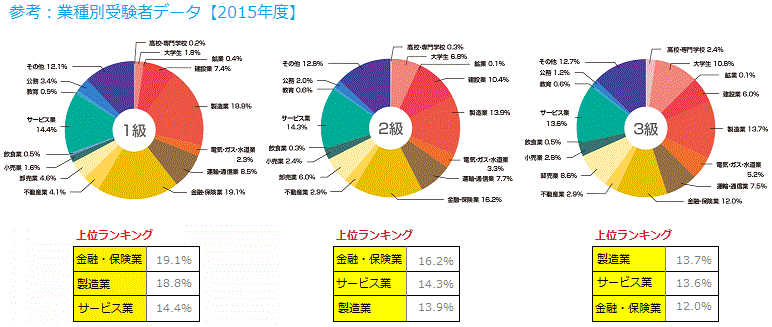
| 階級を上げるごとに学生受験者が減少傾向にあるのは、どうやら本試験で出題される問題文の質(内容)にありそうです。 つまり、冒頭でも触れましたが、ビジネス実務法務検定は、実際のビジネスの現場で役立つ法知識の習得をモットーとした検定試験のため、上位級ほど、よりビジネスパーソンとしての能力が試される実務問題が出題される傾向が強いのです。 そのため、基本的な法知識を単に知っているかどうかを問う3級試験に対し、1級試験ともなると実務レベルでの行動や判断力・対応力が求められるため、社会経験のない学生受験者にとって、この手のスキルアップ試験は、より難易度の高い難しい試験と感じられてしまうようです。 |
そこで、試験に関する情報を、もう少し詳しくまとめてみましょう。
| \ | 制限時間 | 解答形式 | 出題問題数 / 配点 | その他の試験情報 |
| 1級 | 4時間 (共通問題 / 選択問題 各2時間) |
論述 | 4問/200点満点 (1問×50点) |
・共通問題 2問 ・選択問題 4問中から2問解答 |
| 2級 | 2時間 | マークシート | 40問/100点満点 (20問×2点 / 20問×3点) |
・すべて五肢択一問題 |
| 3級 | 2時間 | マークシート | 85問/100点満点 (70問×1点 / 15問×2点) |
・正誤問題 … 30問 ・空欄補充 … 8問(計40個所) ・四肢択一 … 15問 |
特に1級試験は単に法律を知っているというだけでなく、ビジネス上、起こりうるトラブル事例に対し、自分の言葉で表現して解答欄を埋めなければならず、この手の論述問題を苦手とする受検者にとっては、非常に難易度の高く感じる検定試験となっています。
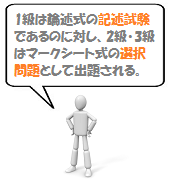 一方、3級試験は2級試験の2倍の数の問題が出題されますが、いずれも法律に関する基礎的知識が身に付いているかどうかを確認する程度のレベルなので、問題数は多いものの、しっかりと勉強していれば十分、制限時間内で解ける問題ばかりです。
一方、3級試験は2級試験の2倍の数の問題が出題されますが、いずれも法律に関する基礎的知識が身に付いているかどうかを確認する程度のレベルなので、問題数は多いものの、しっかりと勉強していれば十分、制限時間内で解ける問題ばかりです。また、各問題に対する配点が低い(1~2点)ため、多少のケアレスミスは合否にあまり影響してきません。
それに対し、2級試験の方は3級試験よりも一歩踏み込んだ法律の理解力も試される問題が出題されているので、難易度が少し上がってきます。
各問題に対する配点も2~3点と高く、3点問題を立て続けに落とすと合格が厳しくなってくるので注意が必要です。
下記にビジネス実務法務検定試験の合格基準を示しましたが、2・3級試験は、総得点の70%以上の得点を得れば合格できる仕組みになっています。
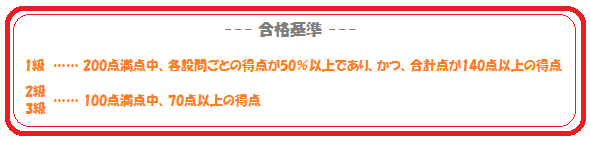
ところが、この手の絶対評価試験には1つ大きな落とし穴があります。
これまでの試験結果を見ても分かるように、2・3級試験の合格率は回によっては激しく変動しているのです。
| つまり、絶対評価試験は、実施年度の出題問題の難易度に合格率が左右されやすい!ということです。 ※ 試験問題が易しい回に当たると、大勢の合格者を輩出するが、問題が難しい回に受験すると合格者が激減する、ある意味〝運〟に左右されやすい試験ということ。 一方、ビジネス実務法務検定1級試験の合格基準は、各設問ごとに最低点(25点)が設けられているため、たとえ総得点が合格基準(140点以上)を満たしていても、得点が最低点に達していない設問が1つでもあれば不合格になってしまいます。 そのため、自分にとっての得意分野と不得意分野を見極めつつ、各設問の正答率が50%を切らないようバランスの良い学習を心がける必要があるため、そういう意味では、非常に難易度の高い試験といえるかもしれません。 |