そこで、気になるのが学科試験の難易度です。
クレーン・デリック運転士の学科試験は難しいのか、それとも初学者が独学でも十分に対応できる問題レベルなのか・・・?
試験制度や過去問を基に、様々な角度から分析し、本試験の難易度について考察しています。
| 問:クレーンのブレーキに関し、誤っているものは次のうちどれか。 (1)電動油圧押上機ブレーキは、制動時の衝撃が少なく、横行用や走行用に多く用いられる。 (2)電磁ディスクブレーキは、ディスクが過熱しやすく、装置全体を小型化しにくい。 (3)電動油圧式ディスクブレーキは、ばねによりディスクをパッドで締め付けて制動し、油圧によって制動力を解除する。 (4)ドラム型電磁ブレーキは、電磁石、リンク機構、ばね、ブレーキシューなどで構成されている。 (5)バンドブレーキは、ブレーキドラムの周りにバンドを巻き付け、バンドを締め付けて制動する構造である。 【平成28年度後期】
|
※補足:試験実施団体の(公財)安全衛生技術試験協会は、半年毎に期間内に実施された試験問題を公式サイトで公開しています。
そのため、与えられた選択肢の中から最も適当な番号を解答用紙にチェックするだけなので、文章力が求められる記述問題に比べると、ビギナー受験者でも解答しやすい試験形式となっています。
次に、こちらの資料をご覧ください。
| 試験科目 | 出題数 | 配点 | 試験時間 |
| クレーン及びデリックに関する知識 | 10問 | 各3点(30点) | 2時間30分 |
| 関係法令 | 10問 | 各2点(20点) | |
| 原動機及び電気に関する知識 | 10問 | 各3点(30点) | |
| クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 | 10問 | 各2点(20点) | |
| 合格基準 | |||
| 全科目の総得点が60%以上、かつ、各科目ごとの得点が40%以上 | |||
※「限定なし」意外の免許試験では、デリック関係の知識・法令は出題されません。
学科試験に関する試験概要ですが、クレーン・デリック運転士の学科試験は4科目で構成されており、各科目10問ずつ出題されるため、計40問(科目免除者は除く)の問題を2時間半で解くことになります。
そのため、1問あたりに割ける平均所要時間は〝3分45秒〟となりますが、見直し時間を考慮する、本試験では、1問当たり3分ジャストで解き進めていくのが理想的かもしれません(もちろん、問題のボリュームや難易度によって多少前後するものですが…)。
1問3分という時間を長いとみるか短いとみるかは人それぞれですが、本試験問題を見る限り、十分に対応できる所要時間であると思われるため、試験時間が短すぎるということはないでしょう。
さて、学科試験で注目すべき点は、1問当たりの配点の高さと合格基準の関係です。
同試験の合格基準によると、合格するには総得点の60%以上の得点が必要ですが、さらに、各科目ごとの得点が40%以上でなければならないといった条件(いわゆる、足切り)が課せられている点に注意しなければなりません。
つまり、仮に総得点で90点以上の高得点を上げたとしても、4科目中1つでも40%を超えない試験科目があると、それだけで不合格となってしまいます。
そのため、全体的に問題数が少なく、かつ、各問題が2~3点の高配点になっている同試験では、1問の出来不出来が合否の明暗を分ける(特に3点問題)こともあるので、ケアレスミスだけは特に防がなければなりません。
また、それと同時に、極端な苦手科目があると、何度も不合格になってしまう恐れがあるので、いかにバランスの良い試験対策を行うかが合格するためのポイントになってきます。
まずは、こちらの資料をご覧ください。
| \ | 平成28年度 〈前期〉 |
平成28年度 〈後期〉 |
|||
| 正誤問題 | ○ | 1問 | 2.5% | 10問 | 25.0% |
| × | 33問 | 82.5% | 21問 | 52.5% | |
| 計算問題 | 4問 | 10.0% | 7問 | 17.5% | |
| 組合せ問題 | 1問 | 2.5% | 2問 | 5.0% | |
| 穴埋め問題 | 1問 | 2.5% | --- | --- | |
特に正誤問題の出題率は高く、全体の7~8割程度を占めますが、平成28年度の後期試験において、これまであまり見られなかった特徴がみられました。
それは〝正しい〟ものを選ばせる問題の数がグッと増えたことです。
これまでの試験問題を振り返ってみると、同試験の正誤問題は、圧倒的に〝誤っている〟ものを選ばせる問題が目立っていたため、この変化は地味ながらも、非常に興味深いところです。
今後も同じような傾向が続くのか、その動向に注目したいところですが、いずれにせよ「正しい」ものと「誤っている」ものとがランダムに出題されるので、本番ではどちらを選ばせる問題なのかということをよく確認し、致命的なケアレスミスをしないよう細心の注意を払ってください。
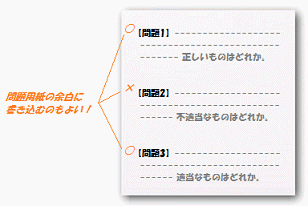
問:力に関し、誤っているものは次のうちどれか。 (1)力の三要素とは、力の大きさ、力の向き及び力の作用点をいう。 (2)一直線上に作用する二つの力の合力の大きさは、その二つの力の大きさの和又は差で求められる。 (3)一つの物体に大きさが異なり向きが一直線上にない二つの力が作用して物体が動くとき、その物体は大きい力の方向に動く。 (4)力を図で表す場合、力の作用点から力の向きに力の大きさに比例した長さの線分を書き、力の向きを矢印で示す。 (5)てこを使って重量物を持ち上げる場合、握りの位置を支点に近づけるほど大きな力が必要になる。 【平成28年度:後期】
問:力に関し、誤っているものは次のうちどれか。 (1)一直線上に作用する二つの力の合力の大きさは、その二つの力の大きさの積で求められる。 (2)力のモーメントの大きさは、力の大きさと、回転軸の中心から力の作用線におろした垂線の長さの積で求められる。 (3)物体の一点に二つ以上の力が働いているとき、その二つ以上の力をそれと同じ効果を持つ一つの力にまとめることができる。 (4)力の作用と反作用とは、同じ直線状で作用し、大きさが等しく、向きが反対である。 (5)力の三要素とは、力の大きさ、力の向き及び力の作用点をいう。 【平成28年度:前期】
|
※攻略ポイント:試験科目ごとに出題される問題自体は、基本的に標準レベルの問題が目立ちますが、稀にほとんどの受験者が自信をもって解答できないような難問が出題されることがあります。しかし、そのような問題(いわゆる、捨て問)は合否を左右することはないため、制限時間がある以上、難問は後回しにするなどのテクニックも必要です(ただし、空欄で提出するのはもったいないので、ヤマ勘でも解答欄は埋めておく!)。
特に重要度の高い問題は、これまでに何度も(数回に1回程度の頻度で出題される問題も…)出題されていますが、この背景には、同試験がほぼ毎月実施されるため、受験者に押えておいてほしいポイントが出尽くした、受験者のスキルを一定に保つため、不公平感を出さないためにも、回によって問題の難易度を極端に上げ下げしにくいといった悩みどころがあるのかもしれません(結果、似たような問題が繰り返される)。
なんにせよ、極端な話、とにかく合格することが最優先!というのであれば、過去問の徹底的な反復練習で合格基準程度の実力は確実に身に付くため、受験者がやるべきことが分かっている以上、試験問題の難易度云々について考察するのは、ナンセンスといった見方もできなくはありません。
問:図のような組合せ滑車を用いて質量40tの荷をつるとき、これを支えるために必要な力Fの値に最も近いものは、次の(1)~(5)のうちどれか。ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、滑車及びワイヤロープの質量並びに摩擦は考えないものとする。 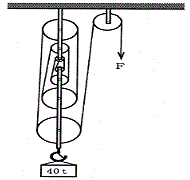 (2)10.0kN (3)43.6kN (4)49.0kN (5)98.0kN 【平成28年度:後期】
問:図のような組合せ滑車を用いて質量20tの荷をつるとき、これを支えるために必要な力Fは、(1)~(5)のうちどれか。ただし、重力の加速度は9.8m/s2とし、滑車及びワイヤロープの質量並びに摩擦は考えないものとする。 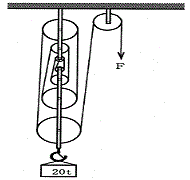 (2)24.5kN (3)28.1kN (4)32.6kN (5)49.3kN 【平成28年度:前期】
|
そのためには、どの部分が正しくて、どこが誤っているのか、それぞれの選択肢をひとつひとつ確認し、本試験で、どのような角度で聞かれても対処できるようにしておくことが大切です。


