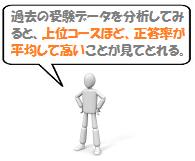 法学検定は受験者の能力に応じて3コース(ベーシック/スタンダード/アドバンスト)に区分されており、上位級ほど難易度は高くなっていますが、過去の試験データを振り返ってみると、試験に合格するには、いずれの階級も概ね50~60%前後の正答率が求められているようです。
法学検定は受験者の能力に応じて3コース(ベーシック/スタンダード/アドバンスト)に区分されており、上位級ほど難易度は高くなっていますが、過去の試験データを振り返ってみると、試験に合格するには、いずれの階級も概ね50~60%前後の正答率が求められているようです。なお、これまでの試験結果を分析してみると、上位級ほど正答率が高くなっているようで、60%を超えることも珍しくありません。
※ 法学検定は試験制度の変更(2012年度以降)により、名称が変わりました(4級 → ベーシック〈基礎〉コース / 3級 → スタンダード〈中級〉コース / 2級 → アドバンスト〈上級〉コース)。
| 実施年度 | ベーシック(旧2級) | スダンダード(旧3級) | アドバンスト(旧4級) | |||
| 合格ライン | 正答率 | 合格ライン | 正答率 | 合格ライン | 正答率 | |
| 2005年 | 33点 | 55% | 45点 | 60% | 32点 | 58% |
| 2006年 | 33点 | 55% | 45点 | 60% | 32点 | 58% |
| 2007年 | 33点 | 55% | 45点 | 60% | 33点 | 60% |
| 2008年 | 31点 | 52% | 45点 | 60% | 37点 | 67% |
| 2009年 | 34点 | 57% | 42点 | 56% | 33点 | 60% |
| 2010年 | 35点 | 58% | 42点 | 56% | 34点 | 62% |
| 2011年 | 34点 | 57% | 45点 | 60% | 33点 | 60% |
| 2012年 | 31点 | 52% | 40点 | 53% | 35点 | 64% |
| 2013年 | 32点 | 53% | 40点 | 53% | 32点 | 58% |
| 2014年 | 30点 | 50% | 42点 | 56% | 35点 | 64% |
| 2015年 | 30点 | 50% | 43点 | 57% | 31点 | 56% |
| 問題数 | 計60問 | 計75問 | 計55問 | |||
※注:ここで紹介する勉強法が絶対!というものではありません。あくまで法学試験対策向けのひとつの勉強方法として参考例を紹介しているだけなので、自分には合ってないと感じた方は自分なりの勉強法を確立してください。
| つまり、本試験問題は、この問題集からの出題(類似問題)が6~7割、問題集の内容をベースとしたアレンジ問題が3割程度出題されるということです。 先にも触れましたが、これまでの試験データを振り返ってみると、法学検定ベーシック&スダンダードコースの合格ラインは正答率52~60%程なので、本試験問題の6~7割が、商事法務研究会発行の『法学検定試験問題集』から出題されているということは、本書さえ、しっかりと学習しておけば、十分、合格圏内の得点が稼げるということになります。 したがって、他社出版の市販テキストや問題集を使った勉強法を行わずとも、商事法務研究会の『法学検定試験問題集』を繰り返し解く反復勉強法だけで十分合格を手にすることは可能ですが、単に合格するだけが目的というよりも、法学を体系的に学びたい(理解したい)という方は、他の市販テキストや法律用語辞典を併用しながら、解らなかった問題(正解選択肢以外の解答のどの部分が誤っているのか?など)をひとつひとつ確認するという作業を組み入れる必要があります。 |
| 一方、法学検定アドバンストコースは、下位級のように「本試験は○○から出題される」といった問題集などは存在せず、『ガイドブック』と『過去問題集』だけが、商事法務研究会より発行されています。 つまり、本試験を受けてみるまで、いったいどのような問題が出題されるのか解らないため、過去問題の丸暗記に頼った勉強法では対処できないのがアドバンストコースの特徴です。 また、過去の試験データを分析してみると、下位コースよりも、より高い正答率が求められているので、その点もそう簡単には合格させてくれない厳しさが垣間見れます。 法学検定アドバンストコースは、下位コースで学ぶべき知識が既に身に付いていることが前提になりますが、まずは出題範囲に含まれている分野の基本書を読み、過去問題を解きながら、各選択肢の内容をひとつひとつチェックしていく(基本書や法律用語辞典などを使って調べる)オーソドックスな勉強法が有効です。 |


