しかし、これらの資格試験に勝るとも劣らない難易度を誇り〝理系資格の最高峰〟との呼び声も高い超難関資格が弁理士です。
そこで、弁理士試験は、いったいどのような理由から、難易度の高い試験と見なされているのか・・・
まずは、そのあたりを少し分析してみることにしましょう。
そのため、1次試験を突破したからと言って気を抜くことは許されず、長期間に渡って高いモチベーションを維持しなければならないことから、合格を手にするまでの道のりが長い(つまり、試験回数が多い)ということが受験者にとってネックのひとつとなっています。
|
|
|
 |
弁理士試験最大の山場は2次試験にあたる〝論文式試験〟にあると言われていますが、合格基準をみると、弁理士試験は総得点だけでなく、各試験科目ごとに最低得点が設けられていることが分かります。
つまり、得意科目で不得意科目をカバーするといったことにも限界があるため、各科目バランスよく勉強して、一定の得点力を身に付けなければならないということです。
そのため、試験科目にひとつでも極端な苦手科目がある受験者にとっては、非常に難易度の高い試験に感じられてしまうおそれがあります。
【必須科目】の合格基準を満たし、かつ【選択科目】の合格基準を満たすこと
|
平成20年度から新たに導入された免除制度により、弁理士試験は、従来の試験制度に比べると受験者の負担が軽くなったと言われています。
| 短答式試験 | 論文式試験 |
| ■特許庁において審判、審査の事務に5年以上従事した者 → 工業所有権に関する法令、工業所有権に関する条約の試験科目免除 ■工業所有権に関する科目の単位を修得し大学院を修了した者(平成20年1月~) → 大学院の課程修了日から2年間、工業所有権に関する法令、工業所有権に関する条約の試験科目免除 ■短答式試験合格者(平成20年度~) → 合格発表日から2年間、短答式試験のすべての試験科目免除 |
≪ 筆記試験 ≫ ■必須科目合格者(平成20年度~) → 合格発表日から2年間、必須科目免除 ■特許庁において審判又は審査事務に5年以上従事した者 ≪ 選択科目 ≫ ■選択科目合格者(平成20年度~) → 合格発表日から永続的に選択科目免除 ■修士又は博士の学位を有する方 ■専門職の学位を有する方 ■他の公的資格者 → 弁理士法施行規則で定める公的資格者(技術士、一級建築士、第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、薬剤師、情報処理技術者、電気通信主任技術者、司法試験合格者、司法書士、行政書士)については、各資格に対応する選択科目免除 |
| 口述試験 | |
| ■特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方 |
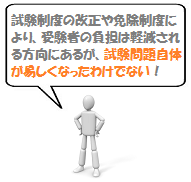 確かに、これまでの受験者データを振り返ってみると、免除者は非免除者に比べ合格率が高くなる傾向にあり、この免除制度があるかないかで受験者の負担が大きく変わってくるのは事実のようです。
確かに、これまでの受験者データを振り返ってみると、免除者は非免除者に比べ合格率が高くなる傾向にあり、この免除制度があるかないかで受験者の負担が大きく変わってくるのは事実のようです。そのため、免除制度をうまく利用することで早期合格が狙いやすくはなりましたが、ここで注意しなければならないのは、必ずしも本試験問題の難易度が下がったわけではない!ということです。
それどころか、むしろ、企業の海外進出によるグローバル化に伴い、弁理士の重要性が増していることから、試験問題自体は難化傾向にあるとも言われています。
| 弁理士試験の難易度が高いと言われる理由のひとつに、受験者層全体の基準レベルが高いということが挙げられます。 これはどういうことかというと、弁理士試験は他の人気士業のように興味本位で受験しにくる人は少なく、特許権や商標権などを特に重要視する大手企業の会社員や、特許事務所関連の受験者が弁理士試験全体の70~80%を占めているのです。 そもそも、大手企業や特許事務所で働く社会人受験者の多くは高学歴の持ち主であることが多く、そのレベルの高い母集団の中で競い合い、成績上位10%圏内に入らなければならないため、単純に合格率では計り知れない難しさがそこにあります。 |
資料1:受験回数別内訳
|
資料2:職業別内訳
|
資料3:出身校別内訳【上位10校】
|
弁理士試験そのものは、どちらかというと〝相対評価〟の性格をもった国家試験なので、受験者は受験者全体との位置関係(能力レベル)を常に意識し、総受験者の上位10%圏内に入るための受験テクニックを必要とします。
| 相対評価試験 | 絶対評価試験 |
| 「受験者の上位●%」といったように成績上位の者から順に合格する試験制度。単純に合格基準さえ満たせば良いという試験ではないため、受験者同士で競い合わなければならず、受験者自身の本当の実力が問われやすい。そのため、母集団の能力が高い(ライバルの成績が上がる)と、基準レベル自体が高くなるが、絶対評価試験のように試験問題の難易度によって合否が左右される…といったことは少なくなる。 | 規定の合格基準(例:100点満点中70点以上で合格)さえ満たしていれば、原則、合格する試験制度。つまり、試験機関が事前に公表している合格基準さえ満たせばよく、受験者同士で競い合うことがない。そのため、試験問題の難易度により、合格者数(合格率)が大幅に変動しやすいのが特徴(試験問題が易しいと大量に合格者数が出るが、試験問題の難易度が高い時期に受験すると合格者数も激減してしまう…いわば運的な要素も強い)。 |
したがって、特に論文式試験では満点を狙うというよりも、いかに上位数%内に食い込むかがポイントになってくるので、余計なことは付け足さず、手堅い答案を作成することが大切です。
|
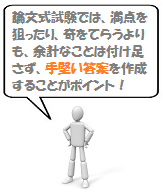 |

