ここ数年、受験者数は徐々に減少傾向にあるようですが、消費生活アドバイザー試験の合格率は、ほぼ安定しており、例年、20%前後で推移しているようです。
|
試験実施機関から委託を受けて 実施している通信講座 |
とはいえ、計算上は4人に3人の受験者が不合格になっている状況からわかるように、容易に合格できる試験ではなさそうです。
そこで、これまでの試験データを基に、消費生活アドバイザー試験の難易度について、少し客観的に分析してみることにしましょう。
| \ | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 司法書士 | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 3.5% | 3.5% | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
| 社会保険労務士 | 7.5% | 7.6% | 8.6% | 7.2% | 7.0% | 5.4% | 9.3% | 2.6% | 4.4% |
| 行政書士 | 6.5% | 9.1% | 6.6% | 8.1% | 9.2% | 10.1% | 8.3% | 13.1% | 10.0% |
| 弁理士 | 5.9% | 8.5% | 8.3% | 9.1% | 10.7% | 10.5% | 6.9% | 6.6% | 7.0% |
| 宅建 | 16.2% | 17.9% | 15.2% | 16.1% | 16.7% | 15.3% | 17.5% | 15.4% | 15.4% |
| 1次試験 | 2次試験 |
| ■筆記試験 ・択一式正誤問題 ・選択式穴埋め問題 ■試験時間 ・1時限 … 生活基礎知識《20問/80分》 ・2時限 … 消費者問題 / 消費者のための行政・法律知識《15問/60分》 ・3時限 … 消費者のための経済知識《20問/80分》 |
■論文式試験 … 2題出題(600~800字程度)/各60分 ・消費者問題《1題》 ・行政知識《1題》 ・法律知識《2題》の計4題より1題選択 ・経済一般知識《1題》 ・企業経営一般知識《1題》 ・生活経済《1題》 ・地球環境問題・エネルギー需給《1題》の計4題より1題選択 ■面接試験 … 面接委員(試験官3人)との個人面接 ・10分程度 / 1人 |
また、詳細については次項で触れますが、1次試験(筆記試験)は、宅建や危険物取扱者試験にみられるような、最もポピュラーなマークシート形式による択一選択制の問題として出題されるわけではない(択2式)ため、迷いが生じる選択肢も少なくないことから、そういう意味では、難易度の高い試験と言えるかもしれません。
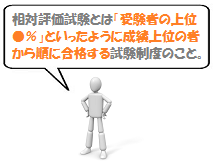 消費生活アドバイザー試験は、下記のような合格基準が公表されていますが、これまでの合格率推移状況を振り返ってみると、1次試験・2次試験、最終合格率はいずれも、ほぼ安定した動きを示しており、最終合格者数は、近年、緩やかに増加傾向が見られますが、概ね300~500人前後で推移しています。
消費生活アドバイザー試験は、下記のような合格基準が公表されていますが、これまでの合格率推移状況を振り返ってみると、1次試験・2次試験、最終合格率はいずれも、ほぼ安定した動きを示しており、最終合格者数は、近年、緩やかに増加傾向が見られますが、概ね300~500人前後で推移しています。また、論文試験や面接試験に関しては、これが正解!といった解答はありません。
以上のような点を踏まえると、消費生活アドバイザー試験は相対評価試験としての性格を持っているようです。
| --- 1次試験 --- 第1時限~3時限の合計得点が、原則として、平均正解率65%程度以上。 --- 2次試験 --- 論文式試験:出題の理解力、課題の捉え方、表現力等を審査し、選択した2題それぞれが5段階評価(A~E)のC以上とする。 面接試験:誠実、円満に加え、秘密保持等の資質、消費生活アドバイザーとして相応しい態度、積極性、見識等について審査し、 面接委員の総合評価が3段階評価(A~C)のB以上とする。 |
| \ | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| 1次試験 | 31.3% | 31.4% | ----- | 32.5% | 27.6% | 32.2% | 31.9% | 27.5% | 28.8% | 29.5% | 31.9% | 32.5% |
| 2次試験 | 48.6% | 49.6% | 50.3% | 51.3% | 56.2% | 54.3% | 51.0% | 56.7% | 61.0% | 64.1% | 62.5% | 61.1% |
| 最終合格率 | 19.1% | 19.0% | 19.8% | 20.1% | 20.2% | 20.2% | 19.2% | 20.9% | 21.0% | 21.4% | 21.6% | 22.0% |
| 最終合格者 | 457人 | 462人 | 500人 | 538人 | 498人 | 474人 | 441人 | 396人 | 306人 | 312人 | 461人 | 514人 |
※ 1次試験合格者は、次年度の受験に限り、1次試験が免除されます。
| 2次試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 平成26年(第35回) | 通常試験者 | 392 | 252 | 64.3% |
| 1次免除者 | 95 | 60 | 63.2% | |
| 平成27年(第36回) | 通常試験者 | 626 | 397 | 63.4% |
| 1次免除者 | 112 | 64 | 57.1% | |
| 平成28年(第37回) | 通常試験者 | 654 | 406 | 62.1% |
| 特例措置 | 77 | 43 | 55.8% | |
| 1次免除者 | 110 | 65 | 59.1% | |
そのため、消費生活アドバイザーのような、それほど難易度の高くない試験は、できるだけ1発合格を目指して本試験に臨んだ方がよさそうです。
|
したがって、そういう考え方・ものの見方(つまり、単純な暗記型試験ではない!)が苦手な受験者にとっては、難易度の高い試験といえるかもしれません。
しかし、これまでの過去問を分析してみると、毎回、同じような論点にスポットを当てた類似問題も多出していることから、過去問を解くことで出題傾向をある程度把握することができる試験といえるでしょう。
参考までに、消費生活アドバイザー試験の過去問を抜粋してみましたが、気付かれた方も多いように、1次試験は単純な択一式問題ではありません。
したがって、分野によっては細部にわたる正確な知識や理解力がないと正解を導き出せない問題もあり、このあたりが非常にやっかいな点といえそうです。
| 漂白剤に関する次の事項のうち、誤っているものを2つ選んで解答欄に番号で記入しなさい。 1.還元型はすべて繊維に使用できるが、色柄物の衣類には使用できない。 2.過炭酸ナトリウム、過酸化水素水を主成分とするものは色柄物にも使用できる。 3.酸化型の酸素系は鉄分や樹脂加工による黄変を回復させることができる。 4.酸化型と還元型があり、酸化型は塩素系と酸素系に分けることができる。 5.次塩素酸ナトリウムの液性は酸性であり、酸性の時は安定であるが、アルカリ性になると塩素ガスを発生する危険がある。 |
| 次の部分中の《ア~オ》の部分に、下記の語群のうち最も適当なものを選んで解答欄に番号で記入しなさい。 家の壁などに結露が起こる原因は、壁に《 ア 》が使われていないか、または、その厚さが不足している場合が多い。窓ガラスの結露防止には、外部にガラス面を保護する《 イ 》を設けたり、内部に天井から床までの厚いカーテンなどで《 ウ 》を固定したり、ガラス自体を《 エ 》にすると効果がある。アルミニウムは《 オ 》が大きいので、内と外を熱的に絶縁した断熱型サッシにして用いるのがよい。 【語群】 1.比重 2.断熱性 3.熱伝導率 4.ルーバー 5.雨戸 6.障子 7.ブラインド 8.乾燥剤 9.断熱材 10.下地材 11.合わせガラス 12.複層ガラス 13.空気層 14.防湿層 15.上端部 |

