コンクリート技士試験の合格基準や配点、採点方法は非公開なので、はっきりしたことは分かっていませんが、〇×式問題は、次のような減点方式の採点法が用いられているという説があります。
そのため、解答に自信がない場合は、下手に答えるよりも、無解答のまま提出してしまった方が得策だという人もいますが、四肢択一式問題の出来不出来によっては、〇×式問題で1点でも多く稼ぐ必要がでてくるので、その辺の判断が難しいところかもしれません。
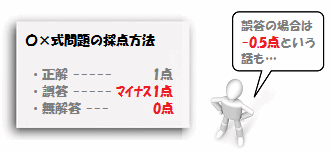 しかし、〇×問題は2択問題なので、正確な知識さえしっかり頭に入っていれば、確実に得点に結びつけることのできる分野です。
しかし、〇×問題は2択問題なので、正確な知識さえしっかり頭に入っていれば、確実に得点に結びつけることのできる分野です。コンクリート技士試験は、あくまでコンクリートに関する基礎知識が身に付いているかどうかを確認するための試験であり、毎年、同じような問題が繰り返し出題されています。
そこで、本試験ではいったいどのようなキーワードが狙われやすいのか、参考までに過去問題を少し振り返ってみましょう。
問:JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定されている記号 SD345 の第2番目のDは、異形棒鋼を表す。 問:水中不分離性コンクリートは、高い材料分離抵抗性を有するため、形状の複雑な陸上構造物にも用いるのがよい。 |
文字通り○か×かの2択問題なので、4択問題よりも楽そうだと考える人も多いようですが、実はこの〇×問題は意外と侮れません。
そこで、なぜ〇×問題が侮れないのか、その理由について、4択問題を例に挙げながら少し補足説明しておきましょう。
まずは、こちらの過去問題をご覧ください。
| 寒中および暑中コンクリートに関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。 1.初期凍害を防止するため、コンクリートの単位水量をできるだけ少なくした。 2.外気温が低かったので、ミキサ内の骨材と水の温度が40℃以下になる範囲で骨材と水を温め,コンクリートの練上り温度を上げた。 3.予め積算温度とコンクリート強度の関係を把握し、養生温度に対応する養生期間を決定した。 4.外気温か高かったので、コールドジョイントの発生を防止するため、打重ね時間間隔を長く設定した。 |
ところが、〇×問題となると、そうはいきません。
なぜなら、四肢択一問題のように、比較するべき肢が他にないので、問題文に書かれている内容に関する正確な知識がなければ自信をもって解答することができないからです。
まして、コンクリート技士試験の〇×問題は、減点方式を採用しているらしいので、ヤマ勘で解答したばっかりに、結果的には誤答で減点になってしまった…!ということも十分ありえます。
| そのため、〇×式問題は、考えようによっては四肢択一式問題よりも正確な知識が求められる、決して侮ってはいけない問題というわけです。 しかし、過去問題を解いてみれば気付くことですが、〇×式問題で出題される内容の大半は、コンクリートに関する基本事項ばかりなので、問題自体のレベルは決して高くありません。 つまり、特に難しいことを聞かれているわけではないので、基本知識さえしっかりと押えておけば、高得点を狙える分野でもあります。 ただ1点、下記に示した本試験問題の出題割合からも分かるように、コンクリートに関する幅広い知識が問われれているので、試験範囲は広く浅く学習しなければなりません。 |
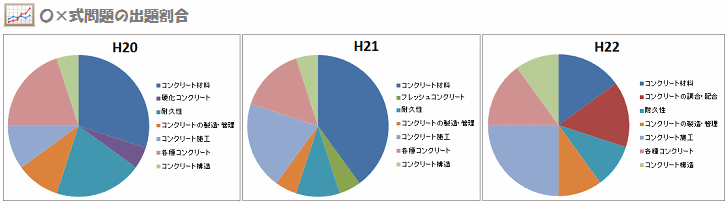
基本的なポイントについてまとめておきます。
ちなみに、〇×式問題と四肢択一式問題で出題される問題レベルや範囲に大きな違いはないので、特に勉強法を変える必要はありません。
- 各種材料(セメントや骨材など)の特徴や性質を混同しないよう正確に理解し、覚える!
- 特殊コンクリートの特徴や注意点、対策を混同しないよう正確に理解しておく!
- コンクリートの劣化のメカニズムや原因をよく理解しておく!
- 鉄筋コンクリートの基本的な設計や特徴を理解しておく!
- 特にJIS A 5308からの出題が目立つので、規定や計量方法などはしっかりと確認しておく!
- 数字や数値などはしっかり覚える!
しかし、全体的に見ると、幅広い分野から、まんべんなく出題されているので、学習すべき範囲は決して狭くはありません。
特に数値に関する問題や施工上の留意点などは狙われやすいので、きちんと整理して関連事項を結びつけながら頭に叩き込んでおくことが大切です。
参考までに、本試験ではいったいどのような問題が出題されているのかを知っていただくために、過去問題をいくつか掲載しておくので、コンクリート技士試験に興味のある方は、チャレンジしてみてください。
| 問1:コンクリートの凝結の始発時間は再振動限界の目安とされるが、コールドジョイントの発生を防止するためには、始発時間より早い時間において新しいコンクリートを打ち重ねるのがよい。
問2:JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート)によれば、スランプフローが50cmの高強度コンクリートは、荷卸し地点での試験値が50cmの±7.5cmの範囲内であれば、スランプフローは合格と判定できる。 問3:質量比で高炉スラブの分量が40%以上の高炉セメントB種を用いる場合は、アルカリシリカ反応性による区分Bの骨材を使用してもよい。 問4:厚さが1.5mの鉄筋コンクリートのスラブであったので、セメントの水和熱によるひび割れを防止するため、普通ポルトランドセメントに替えて中庸熱ポルトランドセメントを用いた。 問5:AE剤によって連行された空気泡は、コンクリート中でボールベアリングの作用をするので、同じスランプのプレーンコンクリートと比較してブリーディング量が多くなる。 問6:JIS A 1101(コンクリートのスランプ試験方法)およびJIS A 1150 (コンクリートのスランプフロー試験方法)で用いるスランプコーンは、同じ形状・寸法である。 問7:細骨材中の0.15mm以下の部分が多いと、AE剤やAE減水剤によって連行される空気泡は、入りにくくなる。 問8:ブリーディングが少ないコンクリートであったので、打込み終了後ただちに金ごてにより、表層にペースト分が集まるようにして仕上げた。 問9:中性化深さは、コンクリートが乾燥状態にあるよりも、湿潤状態にある場合のほうが小さくなる。 問10:500℃に加熱されたコンクリートは、圧縮強度の低下よりもヤング係数の低下が著しい。 問11:アルカリシリカ反応が進行すると、コンクリートのヤング係数が低下する。 問12:通常のコンクリートの引張強度は、圧縮強度の1/6~1/4程度である。 問13:スランプが2.5cmの舗装コンクリートは、ダンプトラックで運搬することができる。 問14:初期材齢時に乾燥を受けて強度発現が停滞したが、その後湿潤養生を継続したため長期強度は回復した。 問15:水セメント比が同じであれば、単位水量が小さいコンクリートほど、乾燥収縮によるひび割れが生じにくい。 問16:スラッジ水を使用する場合、スラッジ固形分率は3%を超えてはならない。 問17:セメント中の酸化マグネシウムの量が多いと、膨張し長期の安定性を損ねる。 問18:石灰石微粉末は、潜在水硬性を発揮してコンクリートの強度を増大させる。 問19:スランプは、所要のコンシステンシーが得られる範囲内で小さい値を選定する。 問20:細骨材の粗粒率が大きいと、コンクリートのポンプ圧送性が悪くなる。 |
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
| ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |

