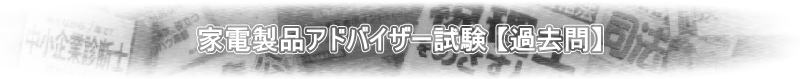そのため、家電製品アドバイザーの称号が欲しいという方は、多かれ少なかれ試験対策というものが必要になってきます。
そこで、本試験では、いったいどんな内容の問題が、どのような形で出題されているのか・・・
受験者が抱えているそのあたりの不安を少しでも取り除くために、過去問を振り返りながら少し分析してみることにしましょう。
| 受験資格 | 特になし | 試験時間 | 75分 / 各科目 |
| 試験日 | 年2回《3月と9月の日曜日》※ ただし、地区限定で水曜日にも実施 | 問題数 | 計20問《200点満点》/ 各科目 |
| 受験料 | AV情報家電・生活家電 …… 各 9,230円 2種目併願 …………………… 15,410円 |
出題形式 | マークシート方式 |
| 試験科目 | AV情報家電 ……「商品知識・取扱」「CS・法規 (共通)」の2科目 生活家電 ……… 「商品知識・取扱」「CS・法規 (共通)」の2科目 |
試験地 | 全国の主要都市 |
※ CSとは?…(Customer Satisfaction:顧客満足)の略。
試験概要については、先に示した通りですが、試験当日の日程については、下記表をご覧下さい。
| AV情報家電 | |||||
| 生活家電 | |||||
| 商品知識・取扱 | CS・法規 | 商品知識・取扱 | |||
| 集合 (9:50) |
試験 (10:00~11:15) |
集合 (11:35) |
試験 (11:45~13:00) |
集合時間 (13:45) |
試験 (13:55~15:10) |
家電製品アドバイザー試験(AV情報家電・生活家電)は、2科目すべてマークシート方式で行われます、
具体的には、下記に挙げるような過去問に見られる正誤問題が中心ですが、他にも以下に示すような出題パターンでの問題も確認されています。
次は、テレビ受信機とテレビ放送について述べたものである。①~④のうち、誤っているものを1つ選び、その番号をマークしなさい。 ① 将来の周波数再利用のために、53ch~62chのチャンネル使用するデジタル放送の中継局は、2011年7月以降のアナログ放送終了後1年の間に、順次52ch以下にチャンネルの切り替えを実施する。このため、機器のチャンネルの再設定が必要となる場合がある。 ② アクトビラビデオ・フルは、ネット・サービスを使用したコンテンツである。映像フォーマットは、MPEG4 AVC/H.264を使用し、ネットワーク回線としては、光回線(FTTH回線:FiberTo The Home)を使用するのが望ましい。 ③ デジタル放送によって行われる最新バージョンのソフトウエアのダウンロードは、通常スタンバイ中のときに行われる。このため、主電源を入れていないと、正常にダウンロードは行われない。 ④ 地上デジタル放送は縮小された画像、もしくは粗い画質の放送に切り替わることがある。地上デジタル放送は雨の影響を受けやすく、豪雨などで電波が弱くなると降雨対応放送に切り替わるためである。 【平成24年度3月試験より】
|
| 正誤問題 | ①~④のうち、正しいもの(誤っているもの)を1つ選べ… |
| ○×判定問題 | 正しいものは①、誤っているものは②、をマークしなさい… |
| 穴埋め問題 | (ア)~(オ)に適切なものを、語群①~⑩から選び、その番号をマークせよ… |
| 組合せ選択問題 | (ア)~(オ)に該当するものを、語群①~⑩から選び、その番号をマークせよ… |
というのも、家電製品アドバイザー試験における出題パターンの中心は正誤問題ですが、設問によって〝適切なもの〟と〝不適切なもの〟とを選ばせる問題(あるいは、正しいものは ①、誤っているものは ② をマークさせる)が混ざって出題されるため、不注意による間違いを起こしてしまいやすいからです。
したがって、この手のマークシート問題を解く際には、最終的な見直し時間を考慮しながら解き進めていくとともに、必ず試験問題用紙にもチェックを入れながら(選択肢すべてに〇×を記入しておく…など)解き進めていくようにしましょう。
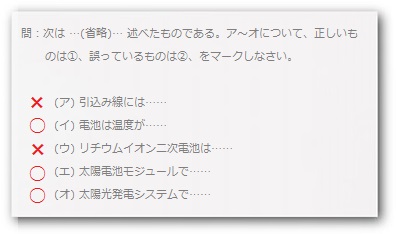
| 家電製品アドバイザー試験で出題される対象機器や項目は以下の通りですが、過去問を振り返ってみると、毎回、同じような問題が形を変えて出題されるケースも目立つようです。 つまり、過去問題に触れておくことで、得点できる内容も少なくない…!ということです。 しかし、家電製品技術は、日々、向上していることから、その辺も意識してか、本試験では最近の技術(知識)に関する問題も出題されます。 したがって、家電製品アドバイザー試験対策向けの教材は、できるだけ最新のテキストや問題集を使うことが大切です。 また、日頃から、AV・デジタル関連の雑誌やウェブサイトをチェックするなり、家電量販店に足を運ぶなりして、最新の家電技術情報にも注目しておくようにしましょう。 |
《試験科目の詳細》
|
特に類似問題が出題されるような試験においては、過去問を解き理解を深めておくことで、得点しやすくなるので、過去数年分の試験問題は必ずマスターするようにしましょう。
問1:次は、接続端子について述べたものである。(ア)~(オ)に適切なものを語群①~⑩から選び、その番号をマークしなさい。 (ア)コンポーネントタイプのCDプレイヤーやMDレコーダー、5.1サラウンドシステムなどのデジタル入出力に使用。 (イ)ポータブル型のCDプレイヤーやMDレコーダーなどで、デジタル入出力に使用。 (ウ)デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ、プリンターなどに使用。 (エ)DVD/HDDレコーダーやデジタルテレビのアンテナ端子に使用。 (オ)電話やデジタルテレビ受信機の双方向番組通信に使用。 《語群》
【平成19年度実施分】
問2:次は、デジタル放送について述べたものである。①~④のうち、誤っているものを1つ選び、その番号をマークしなさい。 ① 地上デジタル放送の電子番組表(EPG)データは、各放送チャンネルから送信され、当日を含め8日分の情報を自動的に取得している。取得した番組表から、簡単に録画予約を行うことができる。 ② 地上デジタル放送を受信する方法として、UHFアンテナで受信する方法とケーブルテレビで受信する方法以外に、最近では光回線を使用して受信する方法もある。専用チューナーを IPネットワークに接続し、地上デジタル放送と同じ番組を視聴できる。また、放送電波(RF信号)を光に変換して伝送する方式もある。 ③ ワンセグ放送は携帯・移動体向けの放送で、一般的には地上デジタル放送の固定受信向け放送と同じ内容の番組を視聴できる。独自の番組も一部の時間帯で放送している。ワンセグ放送が受信できる携帯電話では、双方向サービスを利用することもできる。 ④ 放送している番組を見るには、B-CASカードが必要になる。このカードを挿入していない受信機は、地上デジタル放送やBSデジタル放送に使用される著作権保護技術であるCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応できないため、視聴できない。 【平成24年度実施分】
問3:次は、デジタル放送について述べたものである。①~④のうち、誤っているものを1つ選び、その番号をマークしなさい。 ① モバキャスとは、地上アナログ放送終了後のVHF帯の空きチャンネルを利用した、モバイル機器向けマルチメディア放送サービスの総称である。スマートフォンやタブレット端末向けに、現在NOTTV(ノッティヴィー)が放送を行っている。 ② 地上デジタル放送では、当日を含め7日分の電子番組表情報(EPGデータ)が各放送チャンネルから送信されている。 ③ 現行のハイビジョン放送を超える高画質の4Kテレビ放送は、開始時点においては124/128度の衛星を使ったCSデジタル放送による放送化が計画されている。 ④ 地上・BSデジタル放送の受信方法のひとつに、放送コンテンツをIPパケットに変換して光ファイバーで宅内に引き込む方法(例:ひかりテレビ)がある。このデジタル放送を受信するためには、対応したチューナーあるいは対応したテレビが必要である。 【平成26年度実施分】
|
問4:次は、電気暖房器について述べたものである。(ア)~(オ)について、正しいものは①、誤っているものは②、をマークしなさい。 (ア) 電気カーペットは一線式、二線式とも異常発熱時や強い衝撃を受けた場合に、コードヒーター側の短絡層が溶解したりつぶれたりして発熱線と短絡線間がショートし、コントローラー内の温度ヒューズを溶断させて安全を保っている。 (イ) 電気カーペットを保管する場合、虫食いを防止するために防虫剤を使用し、湿気の少ない場所に保管する。 (ウ) 電気毛布は、ヒーター線の配置密度を胸元や足元で変えられるなどの工夫がされており、胸元、足元を反対にして使わない。 (エ) 洗えるタイプの毛布は、発熱体の入ったまま手洗い(押し洗い)およびドライクリーニングができる。 (オ) クオーツランプヒーターは石英ガラス管を利用したランプヒーターで、視覚的にも暖かさを持ち、外径が小さいことからヒーターユニットの厚さを薄くすることができる。しかし振動、衝撃には弱く、取り扱いには注意が必要である。 【平成19年度実施分】
問5:次は、冷蔵庫について述べたものである。【 ア 】~【 オ 】に該当するものを、語群①~⑩から選び、その番号をマークしなさい。 一般のアルコール温度計を使用して庫内の保存温度を測定する場合、約100ccの水を入れた容器を庫内【 ア 】の中央に置き、その中に温度計の感温部を3時間程度浸しておくことにより、保存温度に近い温度が測定できる。 食品の保存は、密閉容器に入れたりラップをかけたりするとよい。これにより、水分の蒸発やにおいの抑制となり、蒸発器の【 イ 】も減少し省エネ効果につながる。 冷蔵庫は、周囲に【 ウ 】スペースを十分にとる必要がある。カタログの据付寸法図には、最小【 ウ 】スペースを含んだ必要設置スペースの数値を表示している。 冷蔵庫は、一般家庭の食品を冷凍冷蔵保存する目的で造られた製品である。食品以外の薬品や【 エ 】の物は、冷蔵室で保存すると引火、爆発のおそれがあるため、保存してはいけない。また、学術資料などの厳しい管理が必要なものも貯蔵禁止としている。 ドアを閉めると他のドアが一瞬浮く場合がある。これは、ドアを閉めたときの【 オ 】が内部の冷気循環スペースを通りほかの部屋に伝わるためである。食品の詰め過ぎによりドアが内部から押された状態になっていると、ドアが一瞬浮いたときに半ドアとなってしまうことがあるので、食品を整理する必要がある。 《語群》
【平成24年度実施分】
問6:次は、物質の三態と冷蔵庫の仕組みについて述べたものである。(ア)~(オ)について、正しいものは①、誤っているものは②、をマークしなさい。 (ア)冷凍室で長時間貯氷したままにすると、氷が小さくなる。これは融解によって周囲に熱を放出しながら、氷が水蒸気になるためである。 (イ)冷却に氷を用いる冷蔵庫がある。これは、氷が溶ける際に熱を奪う蒸発熱を利用して庫内を冷やす仕組みである。氷点下にならず庫内が乾燥しにくいなどの特徴から、寿司店で寿司だねを保管する用途などで使用される。 (ウ)ものを冷やす方法にペルチェ効果を利用する方法がある。これは、二つの異なる種類の金属を接合し、その間に電流を流すと熱の移動が起こる現象を利用した冷却方法で、圧縮機(コンプレッサー)による振動や作動音がない。レジャー用のドリンククーラーや家庭用のワインセラーなどに使用されている。 (エ)ノンフロン冷蔵庫はノンフロン冷媒とノンフロン断熱材発泡剤を使用している。冷媒のイソブタンと断熱材のシクロペンタンはオゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響も少ない。 (オ)自動製氷方式は給水タンクに水を入れ、冷蔵庫に給水タンクをセットするだけで氷ができ、貯氷ケースに氷がたまる仕組みである。貯氷ケースに氷がたまると定期的に重量センサーで氷の量を確認し、氷があふれないようにしている。 【平成26年度実施分】
|
問7:次は、販売時におけるCSについて述べたものである。①~④のうち、最も適切なものを選び、その番号をマークしなさい。 ① 商品説明にあたっては、お客様の知りたいことを把握したうえで、お客様のニーズに合った商品提案及び機能などを分かりやすい言葉で説明するようにしている。 ② 来客の多い売り場では、初めてのお客様も多く、個々のお客様の性格が分からないので、聞かれたことにだけ答えるようにしている。 ③ 商品説明にあたっては、専門的な知識が豊富で安心してまかせられる店と思われるように、できるだけ専門用語を多用して説明するようにしている。 ④ お客様に満足してもらえる商品説明を行うためには、メーカーが用意した商品説明資料の企画意図を中心に説明するようにしている。 【平成19年度実施分】
問8:次は、接客の基本やマナーについて述べたものである。組み合わせ①~④のうち、不適切なものの組み合わせを1つ選び、その番号をマークしなさい。 (ア)購入を計画して来店したお客様が、気分を害し他店へ回るなどの場合、担当者の基本的な接客マナー欠如が要因となることもある。店にとって大きな損失である。好感を与える基本的な接客マナーには、お客様の購入のお役に立とうという強い気持ちを原点とする基本姿勢が欠かせない。 (イ)来店したお客様の第一印象が、その後の商談にも影響を与えることになる。一斉に挨拶するかどうかの是非はともかく、人の気持ちや意識は相手に伝わりやすい。そのため、それぞれに業務をこなしながらも、入店客には常に「いらっしゃいませ」という、おもてなしの気持ちを持つことが大事である。 (ウ)接客マナーとして、言葉遣いや服装・身だしなみなどが大事といわれるが、これらは時代の変化や社会環境の変化で、大きく変わる。特に若者層の変化は激しい。さらに敬語や丁寧語に違和感を持つ人も増えている。服装も含めもっと自由に変化に対応していくことが、店の側にとっても、お客様にとってもベターである。 (エ)AVや情報通信系デジタル商品の進化は早い。しかし、女性客や中高年客の多くは、基本知識が欠けているため、こちらの説明が理解できず、購入後の再三の相談やクレームにつながり、余分な手間暇を要する結果となる。そのため、こうした商品の購入者には、操作などが分からなくなったらメーカーに相談するよう予め助言している。 (オ)家電品の場合、日常的に消費する食品や日用品の購入と違い、お客様自身の保有知識や判断による適切な商品選択は難しいことが多い。それだけにお客様によっては、ニーズにできるだけ沿った商品を、店側のリードで選んであげることにしている。 《組み合わせ》 ①(ア)と(イ) ②(イ)と(ウ) ③(ウ)と(エ) ④(エ)と(オ) 【平成24年度実施分】
問9:次はデジタル時代のCSについて述べたものである。①~④のうち、誤っているものを1つ選び、その番号をマークしなさい。 ① インターネット通信料金は従量契約の普及により、個々の通信について課金されることはほとんど見られなくなったが、携帯電話やスマートフォンなどの携帯端末では契約によっては受信においてもパケット通信料が発生することがあり、お客様への発信には注意が必要である。 ② ネット販売は始めやすいが、それだけに競争は激しく同じ業態での継続は飽きられ長続きしないケースが多い。顧客に対するCSは目先の満足感だけを提供することだけではなく「安定した継続経営による安心感(信頼感)」を発揮することも重要である。 ③ 商品情報においては、従来のメーカー主導の情報だけではなく、口コミ等の第三者によって選別された情報も容易に収集することができ、よりお客様の視点に立った商品提案が可能となっている。 ④ 商品提案においては、数量や表現に限度のある従来の紙カタログに比べ、タブレット端末等の活用による動画でのプレゼンや電子カタログによる直感的な説明もできるようになってきた。 【平成26年度実施分】
|

| AV情報家電 | 問1:(ア)③ (イ)⑩ (ウ)⑤ (エ)⑦ (オ)② 問2:④ 問3:② |
| 生活家電 | 問4:(ア)① (イ)② (ウ)① (エ)② (オ)② 問5:(ア)⑥ (イ)④ (ウ)③ (エ)⑩ (オ)⑦ 問6:(ア)② (イ)② (ウ)① (エ)① (オ)② |
| CS・法規 | 問7:① 問8:③ 問9:① |