秘書として働くためには、公益財団法人・実務技能検定協会が主催する
秘書検定の資格が無ければならない!というわけではありませんが、実務で役立つ職務知識やビジネスマナー(言葉使いなど)が学べるとして、社会経験のない学生(全体の約8割)を中心に受験される方が多いようです。
秘書検定は、受験者の能力に応じて4クラス(1級|準1級|2級|3級)に分かれますが、社会経験のない学生が、いきない1級試験に挑戦したとしても、合格する可能性は低い(もちろん、ゼロではありませんが…)ので、まずは入門レベルの
3級合格を目指し、1ランクずつステップアップしていった方が賢明かと思われます。
そこで、秘書検定3級とは、いったいどのような試験制度で、どんな問題が出題されるのか・・・?
本試験で実際に出題された問題(いわゆる
過去問)を基に、3級試験の全体像(試験内容や難易度など)について、把握しておきましょう。

秘書検定の試験内容は、階級によって異なってきますが、
3級は筆記試験によるペーパーテストのみで合否判定が行われます。
なお、検定試験の出題範囲に関しては、各級共通であり、ほぼ変わりありません。
| 1級 |
筆記試験 |
・記述式 |
出題範囲《各級共通》
Ⅰ.必要とされる資質
Ⅱ.職務知識
Ⅲ.一般知識
Ⅳ.マナー接遇
Ⅴ.技能 |
| 面接試験 |
・ロールプレイング形式 |
| 準1級 |
筆記試験 |
・マークシート方式 [5肢択一]
・記述式 |
| 面接試験 |
・ロールプレイング形式 |
| 2級 |
筆記試験 |
・マークシート方式 [5肢択一]
・記述式 |
| 3級 |
筆記試験 |
・マークシート方式 [5肢択一]
・記述式 |
そのため、出題される問題のレベル(難易度)を変える(上位ランクほど、より深く高度な知識・技能が求められる)ことでクラス分けしているというのが秘書検定の特徴といえるでしょう。
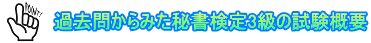
秘書検定の
過去問題を振り返ってみると、3級試験の出題問題数は《計35問 / 120分》ですが、その大半の問題は
マークシート方式(5肢択一)で出題されています。
また、試験内容は大きく5つの分野で構成されていますが、過去問を分析してみると、下記のような配分で出題されていることが分かります。

| \ |
理論科目 |
実技科目 |
| 必要とされる資質 |
職務知識 |
一般知識 |
マナー・接遇 |
技能 |
択一問題
(マークシート) |
5問 |
5問 |
3問 |
10問 |
8問 |
| 記述問題 |
----- |
----- |
----- |
2問 |
2問 |
|
ここでひとつ注目すべき点は、秘書検定の〝合格基準〟です。
秘書検定には合格基準があり、理論科目と実技科目ごとに合格に必要とされる最低点が設けられているのです。

理論科目、実技科目ともに60%以上の得点 |
つまり、仮に理論科目が合格基準を満たしていたとしても、実技科目の方が基準点を下回っていると不合格になってしまうため、両科目ともにバランスの良い学習を心がけることが大切だということです。

秘書検定3級は、一部の記述問題を除くと、その大半はマークシート方式で出題されるため、実務経験のない学生受験者にとっては〝面接試験〟がない分、受けやすい試験制度といえそうです。
しかし、先にも述べたとおり、理論科目と実技科目、それぞれに一定の合格基準が設けられていることから、両科目、バランス良く学習し、極端な苦手科目を作らないようにしなければなりません。
特に実技科目に比べ、理論科目は対策が立てづらい上に面白みに欠けるため、試験対策に苦労されている受験者も少なくないようです。
しかし、秘書検定は合格者のレベルを、ある程度安定させる必要上、
過去問が重視される傾向が強いことから、比較的、試験対策の立てやすい試験といえるので、数年分の本試験問題をまとめて収録した市販の過去問題集等を利用することで、独学でも十分合格の狙える試験といえるでしょう。
参考までに、秘書検定3級では、実際にどのような問題が出題されているのかを肌で感じ取ってもらうため、本試験で出題された問題の一部をいくつか載せておくので、興味のある方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

問1:秘書A子が先輩の急ぎの仕事を手伝っていたとき、上司から私用を指示された。急ぎの仕事はあと1時間ほどかかりそうである。このような場合どのように対処したらよいか。次の中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。
1)上司には承知したと言って、先輩にどのようにしたらよいか相談する。
2)上司にいつまでにすればよいか確認し、急がないようなら急ぎの仕事を続ける。
3)上司に急ぎの仕事が終わるおおよその時間を言って、私用はその後でよいか尋ねる。
4)自分は上司の秘書なので、先輩に急ぎの仕事は中断させてもらうと言って私用を先に行う。
5)さほど時間はかからないことなので、先輩に切りのよいところで中断して私用を済ませてもよいか尋ねる。
【必要とされる資質:理論】
問2:新人秘書A子は先輩から、秘書の仕事には特に教えられたり指示されていなくても、自分で考えて積極的にしないといけないこともあると言われた。次はA子が、それはどのようなことか考えたことである。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。
1)上司が出張中で時間に余裕があるときは、上司のロッカーの中を整理しておくなどのことではないか。
2)よく指示される仕事は、仕事ごとに手順をマニュアル化しておき、ミスなく速くするなどのことではないか。
3)外出するときは行き先を言って、ついでに済ませる用事はないか周りの人に尋ねるようにするなどのことではないか。
4)郵便にはいろいろな書類や送り方があるので、発送物を適切に送るために郵便の知識を得ておくなどのことではないか。
5)上司から仕事を指示されたときは、忘れたり期日を間違えたりしないように、自分の予定表に記入しておくなどのことではないか。
【職務知識:理論】
問3:次はそれぞれ反対の意味の用語の組み合わせである。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。
1)債権 ――― 債務
2)増益 ――― 減配
3)栄転 ――― 左遷
4)需要 ――― 供給
5)採用 ――― 解雇
【一般知識:理論】
問4:次は新人秘書A子が先輩から、電話をかける前に確認することとして教えられたことである。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。
1)必要とする資料は手元に用意したか。
2)メモ、筆記具は手近なところにあるか。
3)どこと電話中かが分かるようにしてあるか。
4)かけようとしている電話番号に間違いはないか。
5)電話機のそばに湯飲み茶わんなどは置いていないか。
【マナー・接遇:実技】
問5:次は秘書A子が、会議の資料を準備するときに心掛けていることである。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。
1)資料は、予備として会議の出席者数より二、三部多く用意するようにしている。
2)資料の大きさがまちまちのときは、大きさをそろえた方がよいか上司に確認している。
3)丁合を取った資料をホチキスでとじるときは、横書き資料の場合は右上を斜めにとじている。
4)資料をセットするときは、それぞれのページのコピーの枚数を確認してから丁合を取っている。
5)部外秘の資料をコピーしていてミスコピーが出てしまったときは、シュレッダーで処理するようにしている。
※ 「丁合を取る」とは、印刷(コピー)したものを、ページ順にそろえること。
【技能:実技】
|
問6:次は秘書A子が、来客と上司にお茶のお代わりを入れようとしている絵であるが、上司が困った顔をしている。① それはなぜだと思うか。また、② A子はどのようにすればよいかを答えなさい。
【マナー・接遇:実技】
問7:秘書A子は上司から、下のようにあて名が印刷してある返信のはがきを渡され、出しておいてもらいたいと言われた。このような場合、相手に対する敬称はどのように書けばよいか。はがきに書き入れなさい。
【技能:実技】
|
| 問1 |
問2 |
問3 |
問4 |
問5 |
問6 |
問7 |
| 4 |
1 |
2 |
3 |
3 |
① その場で、お茶のお代わりを
急須から直接、注いでいるいる
ため。
② 先に出した茶碗を下げ、新し
く入れてきたお茶と差し替える。 |
 |




