証券アナリストの資格を取得(付与)するには、公益社団法人・日本証券アナリスト協会が主催する通信教育講座の受講義務がありますが、単にこの指定講座を修了しただけではダメで、その講座に基づく証券アナリスト試験に合格しなければなりません。
 |
 |

|
|
終了
 |
|
|
|
《科目合格制》

全3科目合格 |

|
|
終了
 |
|
|
|
合格

実務経験
(3年以上) |
 |
つまり、証券アナリストになるには、最低でも1年以上の長期にわたっての対策が必要になってくるので、モチベーションを維持するためにも、できることなら試験は一発合格を目指したいところです。
そこで、これまでの試験データを基に、証券アナリスト試験の難易度について少し客観的に分析してみたいと思います。

(公社)日本証券アナリスト協会が主催する
証券アナリスト試験の1次レベルは、現在、年2回(春と秋)、2次レベルは年1回(初夏)行われていますが、ここ数年間(2003年以降)における1次・2次レベル別の試験結果は次のとおりです。

| \ |
春(4月) |
秋(9月または10月) |
| 受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
| 2003年 |
受験者数(15,376) / 合格者数(7,327) / 合格率(47.7%) |
| 2004年 |
受験者数(11,828) / 合格者数(5,206) / 合格率(44.0%) |
| 2005年 |
受験者数(11,276) / 合格者数(5,075) / 合格率(45.0%) |
| 2006年 |
10,459 |
5,024 |
48.0% |
5,063 |
2,224 |
43.9% |
| 2007年 |
9,447 |
4,171 |
44.2% |
5,600 |
2,509 |
44.8% |
| 2008年 |
9,494 |
4,425 |
46.6% |
5,986 |
2,773 |
46.3% |
| 2009年 |
9,977 |
4,638 |
46.5% |
6,815 |
3,361 |
49.3% |
| 2010年 |
8,924 |
4,173 |
46.8% |
5,641 |
2,641 |
46.8% |
| 2011年 |
7,365 |
3,641 |
49.4% |
4,740 |
2,216 |
46.8% |
| 2012年 |
6,224 |
2,838 |
45.6% |
4,265 |
2,143 |
50.2% |
| 2013年 |
5,993 |
2,870 |
47.9% |
4,306 |
2,183 |
50.7% |
| 2014年 |
6,310 |
3,106 |
49.2% |
4,671 |
2,329 |
49.9% |
| 2015年 |
6,834 |
3,413 |
49.9% |
4,651 |
2,308 |
49.6% |
| 2016年 |
7,066 |
3,743 |
53.0% |
5,000 |
2,621 |
52.4% |
※ 2006年度以降、新プログラム(通信講座)の開始に伴い、試験は年2回へ増加
|
このデータによると、1次試験は秋に比べ、春の方が受験者数が多くなる傾向が見られるものの、試験
合格率に関しては、季節に関係なく、比較的、安定した推移(概ね40%台)を示しているようです(ただし、近年は上昇傾向にある…)。
また、証券アナリストは、一般的には難易度の高い難しい試験と思われていますが、この種の資格試験の合格率としては、比較的、高い水準(40%台後半)をキープしていることから、数値の点からみると、想像以上に難しい試験ではないことが伺えます。
一方、2次試験における近年の合格率推移状況は次のとおりです。
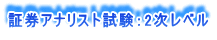
| \ |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
| 2003年 |
3,901 |
1,528 |
39.2% |
(-1.6) |
| 2004年 |
3,496 |
1,586 |
45.4% |
(+6.2) |
| 2005年 |
2,999 |
1,116 |
37.2% |
(-8.2) |
| 2006年 |
2,731 |
1,043 |
38.2% |
(+1.0) |
| 2007年 |
2,978 |
1,124 |
37.7% |
(-0.5) |
| 1,923 |
661 |
34.4% |
(-3.3) |
| 2008年 |
2,499 |
942 |
37.7% |
(+3.3) |
| 2009年 |
2,922 |
1,297 |
44.4% |
(+6.7) |
| 2010年 |
3,108 |
1,470 |
47.3% |
(+2.9) |
| 2011年 |
2,904 |
1,302 |
44.8% |
(-2.5) |
| 2012年 |
2,742 |
1,203 |
43.9% |
(-0.9) |
| 2013年 |
2,536 |
1,168 |
46.1% |
(+2.2) |
| 2014年 |
2,376 |
1,175 |
49.5% |
(+3.4) |
| 2015年 |
2,339 |
1,127 |
48.2% |
(-1.3) |
| 2016年 |
2,410 |
1,159 |
48.1% |
(-0.1) |
|
2次試験は、1次試験にあたる全3科目(「証券分析とポートフォリオマネジメント」「経済」「財務分析」)をパスし、さらに2次レベルの指定の通信教育講座を修了しないと受験資格がありません。
そのためか、受験者数自体は減少していますが、試験合格率に関しては、1次ほどではないにしろ、そこそこ高水準で推移していることが見てとれます。
ちなみに、証券アナリスト試験は、新カリキュラムへの移行により、2007年度のみ、2次試験も年2回実施(カリキュラムの変更に伴う受験者間の不平等感をなくすための措置)されていますが、合格率も含め、これまでのところ、カリキュラム変更による試験への影響はさほどないように感じられます。

年度によって多少のブレは見られるものの、
証券アナリスト試験の
合格率は、比較的、安定した推移を示しています。
|
|
|
平均値 |
| 1次試験 |
春 |
45.6% |
47.9% |
49.2% |
49.9% |
53.0% |
| 秋 |
50.2% |
50.7% |
49.9% |
49.6% |
52.4% |
|
 |
49.1%
50.6% |
| 2次試験 |
43.9% |
46.1% |
49.5% |
48.2% |
48.1% |
|
 |
47.2% |
これは、証券アナリスト試験が下記に示した合格基準によって合否が決まる〝相対評価(受験者の上位●%といったように成績上位者から順に合格する試験制度)〟試験だからということも大きく影響していると考えられますが、ここで注目すべきは、相対評価でありながら、合格率が、比較的、高い水準で推移しているという点です。
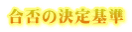
 1次レベル … 「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」は180点、「財務分析」と「経済」は各90点を満点とし、各科目とも上位一定割合の受験者の平均得点を基準として決定 1次レベル … 「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」は180点、「財務分析」と「経済」は各90点を満点とし、各科目とも上位一定割合の受験者の平均得点を基準として決定
 2次レベル … 4科目総合で420点を満点とし、上位一定割合の受験者の平均得点を基準として決定。ただし、4科目の総合得点が試験担当委員会により決定された合格最低点以上であっても「職業倫理・行為基準」の得点が一定の水準に達しない場合は不合格。 2次レベル … 4科目総合で420点を満点とし、上位一定割合の受験者の平均得点を基準として決定。ただし、4科目の総合得点が試験担当委員会により決定された合格最低点以上であっても「職業倫理・行為基準」の得点が一定の水準に達しない場合は不合格。
※試験科目と配点:「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」「コーポレート・ファイナンスと企業分析」「市場と経済の分析」360点、「職業倫理・行為基準」60点 |
つまり、この種の相対評価試験においては、試験そのもののデキ(正解率)よりも、全受験者の中で、自分がどのポジション(順位)にいるのかが重要なのであって、なにもペーパーテストで満点を目指す必要はないということです。
※ 試験範囲をすべて完璧にマスターしようとすると、非常に高度な知識が求められる難易度の高い試験ですが、あくまで試験合格が目的であれば、話が変わってくるということです。
また、公表されている試験結果は、勉強不足(仕事の関係上、半ば強制的に受けることになった…といった方もいるのが現状)の受験者等も含めたデータなので、真剣に試験対策に取り組んでいる方からすれば、合格率はさらに上がると考えられます。
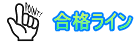
試験の合否にかかわる判定基準については、受験案内等にも明記されていますが、明確な合格ライン(合格点)となると非公開の立場をとっています。
そのため、証券アナリスト試験におけるはっきりとした合格ラインは不明ですが、これまでの試験結果や受験経験者の意見などを踏まえると、1次試験に関しては概ね6割、2次試験に関しては概ね5割以上の得点がひとつの目安となりそうです。
ただし、ここ最近の試験結果を分析してみると、平均点がやや上昇している節も見られるので、このラインを超えていたから大丈夫!といった保証はありません。
過去問(経済)
市場均衡と市場の失敗に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
A.外部効果とは、市場での取引を通さずに直接に他の経済主体に及ぼす効果である。(← 正解)
B.クールノー競争とは、価格を戦略変数とする寡占競争のことである。
C.独占市場で決まる生産量は、一般に、総余剰を最大にする水準よりも多い。
D.公共財供給の場合、対価を支払わない人達の消費を排除することは容易である。
【H22年度より一部抜粋】
|




