そうなると、受験者が少なからず気になるのが試験の難易度ではないでしょうか。
一般的に国家資格に属する試験問題は、公的資格や民間資格に比べると難しいと言われますが、過去の受験者データを振り返ってみると、潜水士試験の合格率は例年70~80%台と非常に高い水準で推移しており、どうやら難関試験というわけでもなさそうです。
しかし、かといって簡単に合格できるような易しい試験でもないため、いったいどのくらい難しい試験なのか、様々な角度から本試験の難易度について考察してみました。
| 問:気体の性質に関し、誤っているものは次のうちどれか。 (1)酸素は、無色・無臭の気体で、可燃物の燃焼を支える性質があるが、酸素そのものは燃えたり、爆発することはない。 (2)窒素は、常温では科学的に安定した不活性の気体である。 (3)ヘリウムは、質量が極めて大きく、他の元素と化合しにくい気体で、呼吸抵抗は少ない。 (4)一酸化炭素は、無色・無臭の有毒な気体で、物質の不完全燃焼などによって発生する。 (5)空気は、酸素、窒素、アルゴン、二酸化炭素などから構成される。 【平成29年:上半期試験問題より抜粋】
|
※補足:潜水士試験の試験問題は、安全衛生技術試験協会が公式サイトで公開(直近の上半期と下半期の2回分)しています。
そのため、適当な番号をチェックするだけなので、記述式問題とは違い、知らない問題だとまったく答えられないということはなく、ビギナー受験者でも解答しやすい試験形式となっています。
次に、こちらの資料をご覧ください。
| 試験科目 | 出題数 | 配点 | 試験時間 |
| 潜水業務 | 10問 | 30点 | 2時間 |
| 送気、潜降及び浮上 | 10問 | 25点 | |
| 高気圧障害 | 10問 | 25点 | 2時間 |
| 関係法令 | 10問 | 20点 |
つまり、学科試験だけで合否判定を行うことになります。
試験は4科目で構成されており、各科目10問ずつ出題されるため、計40問の問題を4時間かけて解くことになりますが、見直し時間等を考慮すると、本試験では、1問当たり5分前後で解き進めていくのが理想的かもしれません(もちろん、問題の内容やボリューム、難易度によって変動しますが…)
1問5分という所要時間を長いと感じるか、短いと感じるか、その感覚は人それぞれかもしれませんが、5肢択一のマークシート形式の試験であるという点や問題のボリューム、内容(難易度)などを考慮すると、4時間という試験時間はどう考えても長く、実際、本試験会場では時間を持て余し、途中退室する受験者は少なくありません。
そのため、潜水士試験においては、試験時間が短くて困るといった心配は無用です。
しかし、潜水士試験に効率よく合格するためには、次の3つの点をしっかりと押さえた上で試験対策を行うことが大切です。
まず1つ目は、1問当たりの配点の高さです。
先にも説明したように、潜水士試験は1問1点の100点満点ではなく、1問あたりの配点が2~3点とやや高めに設定されているため、1つのミスが合否を左右する場合もあるということをまずは知っておいてください。
そして、2つ目は合格基準です。
試験に合格するには60%以上の得点が条件となりますが、実は総得点だけでなく、各科目にも合格ラインが設けられているのです。
|
全科目の総得点が60%以上、かつ、各科目ごとの得点が40%以上 |
そのため、出題問題数が少ない同試験では、1問の出来不出来が致命傷になることもあるので、特に得点の高い問題のケアレスミスだけは絶対に防がなければなりません。
また、極端な苦手科目があると、それだけで不合格になるリスクが高まるため、いかにバランスの良い試験対策を行うかが合格するためのポイントになってきます。
しかし、他の難関資格と言われる国家試験に比べると、潜水士試験の合格基準は60%(各科目40%)と緩めに設定されているので、見方を変えれば、全体の4割(各科目は5~6問)は間違えても合格することができるため、合格基準を必要以上に気にすることはありません。
さらに受験者が試験対策を行う前に押えておきたい3つ目は、各科目の配点比率です。
同試験は、問題数こそ各科目10問で構成されていますが、実は配点は科目によって異なってきます(「潜水業務」は「関係法令」の1.5倍!)。
つまり、配点の高い分野で得点を稼いでしまった方が何かと楽なので、短期間で効率よく合格を目指すのであれば、苦手科目は足切りラインに引っ掛からない程度の学習にとどめ、配点の高い分野を得意科目にしてしまった方が良い場合もあるということです。
まずは、こちらの資料をご覧ください。
| \ | 潜水業務 | 送気・潜降・浮上 | 高気圧障害 | 関係法令 | 合計 | ||
| 正誤問題 | ○ | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 34問 | 85.0% |
| × | 8問 | 7問 | 8問 | 7問 | |||
| 組合せ問題 | ---- | 1問 | ---- | 2問 | 3問 | 7.5% | |
| 穴埋め+組合せ問題 | 1問 | ---- | 1問 | ---- | 2問 | 5.0% | |
| 計算問題 | ---- | 1問 | ---- | ---- | 1問 | 2.5% | |
各出題パターンの比率は、回によって異なってくるため、毎試験、完全に一致するわけではありませんが、過去数年分の試験問題を振り返り分析してみた限りでは、正誤問題中心(約7~8割)の試験であるということは間違いなさそうです。
特に〝誤っているもの〟を選ばせる問題が目立ちますが、中には〝正しいもの〟を選ばせる問題もランダムで出題されているので、正誤どちらの解答を求められているのか、問題文は最後まで良く読み、ケアレスミスだけはしないようくれぐれも気を付けなければなりません(問題文にある〝正しいもの〟〝誤っているもの〟の下にラインを引いたり、余白に○×をメモしておくのも良い!)。
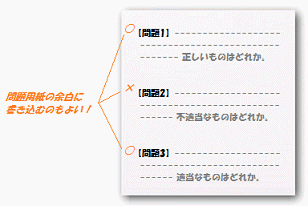
問:潜水による耳の障害に関し、誤っているものは次のうちどれか。 (1)中耳腔は、管によって咽頭と通じているが、この管は通常は閉じている。 (2)耳の障害を防ぐため、耳抜きによって耳管を開き、鼓膜内外の圧調整を行う。 (3)耳の障害の症状として、鼓膜の痛みや閉塞感のほか、難聴を起こすこともあり、水中で鼓膜が破裂するとめまいを生じることがある。 (4)圧力の不均衡による内耳の損傷を防ぐには、耳抜き動作は強く行うほど効果的である。 (5)風邪をひいたときは、炎症のため咽頭や鼻の粘膜が腫れ、耳抜きがしにくくなる。 問:潜水業務において、法令上、特定の設備・器具については一定期間ごとに1回以上点検しなければならないと定められているが、次の設備・器具とその期間との組合せのうち、誤っているものはどれか。 (1)空気圧縮機 ………………………………………… 1か月 (2)送気する空気を清浄にするための装置 ………… 1か月 (3)水中時計 …………………………………………… 3か月 (4)送気量を計るための流量計 ……………………… 6か月 (5)ボンベ ……………………………………………… 6か月 問:圧力の単位に関する次の文中の[ ]内に入れるA及びBの数値の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。 「圧力計が50barを指している。この指示値をSI単位に換算すると[ A ]MPaとなり、また、この値を気圧の単位に換算するとおおむね[ B ]atmとなる。」 (1)A = 0.5 B = 0.5 (2)A = 0.5 B = 5 (3)A = 5 B = 5 (4)A = 5 B = 50 (5)A = 50 B = 50 |
水中という特殊な環境下での作業が中心となるため、日常生活ではあまり使わないような用語が目立ちますが、潜水士として作業するために欠かせない基本的な専門用語や知識を問う素直な問題が目立つ(数字や設備・器具などに関する知識は正確に暗記し、専門用語は意味を理解することが重要!)ため、問題自体の難易度は決して高くありません。
そもそも、潜水士試験は合格率の高さからも読み取れるように、落とすための試験ではありません。
つまり、潜水士として一定レベルの知識さえ身に付いていれば、合格できるレベルの問題で構成されているため、一定のサイクルで類似問題が出題される傾向の強い試験です。
そのため、まったく知識のないゼロからはじめるビギナー受験者であっても、極端な話し、過去問を中心に勉強を進めれば、合格するだけの実力(得点)は必ず身に付きます。
ただ、潜水士試験の勉強を行う上で、少しやっかいなのが〝潜水物理学〟に関する分野かもしれません。
参考までに、潜水士試験で求められる知識(原理・法則)を挙げてみましょう。
そのため、物理を苦手とする文系出の受験者にとっては、この種の問題が出されるとさっぱり分からず、難易度が高い試験と感じてしまう人も多いようですが、基礎さえ理解してしまえば解けてしまうような易しい問題も出題されているので、合格をより確実なものとするためにも、ひととおり学習した上で本試験に臨むことをおススメします。
毎分20Lの呼吸を行う潜水作業者が、水深20mにおいて、内容積14L、空気圧力19MPa(ゲージ圧力)の空気ボンベを使用してスクーバ式潜水により潜水業務を行う場合の潜水可能時間に最も近いものは次のうちどれか。ただし、空気ボンベの残圧が5MPa(ゲージ圧力)になったら浮上するものとする。 (1)16分 (2)32分 (3)44分 (4)48分 (5)98分 |
