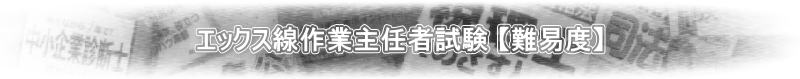過去の試験データを振り返ってみると、エックス線作業主任者試験の合格率は、概ね50%台で推移しており、決して難関試験というわけではありませんが、かといって簡単に合格できるような易しい試験でもなさそうです。
そこで、エックス線作業主任者試験は、いったいどれくらい難しいのか・・・
試験制度や過去問を分析し、本試験の難易度について考察してみました。
| 問:エックス線に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)エックス線は、荷電粒子の流れである。 (2)エックス線は、直接電離放射線である。 (3)エックス線は、波長が可視光線より短い電磁波である。 (4)エックス線の光子は、電子と同じ質量をもつ。 (5)エックス線は、磁場の影響を受ける。 【平成29年:前期試験問題より抜粋】
|
※補足:試験実施団体である安全衛生技術試験協会は、半年毎に直近の試験問題を公式サイトで公開しています。
そのため、予め与えられた選択肢の中から最も適当だと思われる番号を解答用紙にチェックするだけなので、記述式問題とは違い、まったく答えられないということはないため、ビギナー受験者でも解答しやすい試験形式となっています。
次に、こちらの資料をご覧ください。
| 試験科目 | 出題数 | 配点 | 試験時間 |
| エックス線の管理に関する知識 | 10問 | 30点 | 4時間 (午前:2時間 / 午後:2時間) |
| 関係法令 | 10問 | 20点 | |
| エックス線の測定に関する知識 | 10問 | 25点 | |
| エックス線の生体に与える影響に関する知識 | 10問 | 25点 | |
| 合格基準 | |||
| 全科目の総得点が60%以上、かつ、各科目ごとの得点が40%以上 | |||
そのため、計算上、1問あたりの持ち時間は〝6分〟となりますが、見直し時間を考慮すると、本試験では1問当たり5分程度で解き進めていくのが理想的かもしれません(もちろん、問題のボリュームや難易度によって多少変動しますが…)。
1問5分という時間を長いとみるか短いとみるか、その感覚は人それぞれかもしれませんが、本試験問題の内容(難易度)やマークシート試験であるという点を踏まえると、40問で4時間はどう考えても長すぎで、実際、本試験会場では時間を持て余し、途中退室する受験者は少なくありません。
そのため、試験時間が短すぎるという心配はありませんが、エックス線作業主任者試験対策を行う上で、受験者がまずしっかりと押さえておきたい点は次の3つです。
まず1つ目は、1問当たりの配点の高さです。
エックス線作業主任者試験は出題問題数が40問と少ないため、1問あたりの配点が2~3点と高めに設定されており、1つのミスが致命傷になる恐れがあるということをまずは知っておいてください。
そして、2つ目は合格基準です。
試験に合格するには60%以上(60点)の得点が必要ですが、総得点だけでなく、各科目ごとの得点が40%以上でなければならないといった条件(いわゆる、足切り)が課せられている点にも注意しなければなりません。
つまり、仮に総得点で高得点を獲得しても、40%に満たない試験科目が1つあっただけで不合格となってしまいます。
そのため、出題問題数が少ない同試験では、1問の出来不出来が合否の明暗を分けることもあるので、ケアレスミス(特に3点問題)だけは絶対に防がなければなりません。
また、それと同時に、極端な苦手科目があると、何度も不合格になってしまう恐れがあるので、いかにバランスの良い試験対策を行うかが合格するためのポイントになってきます。
しかし、合格基準が70~80%と高めに設定されている国家試験も珍しくはない中、エックス線作業主任者試験の合格基準は、比較的緩めであり、合格しやすい試験であることは間違いありません。
さらに受験者が注目すべき点は、各科目の配点比率です。
同試験は、問題数こそ各科目10問で構成されていますが、配点は科目によって異なってきます(「エックス線の管理」は「関係法令」の1.5倍!)。
つまり、何が言いたいのかというと、配点の高い分野で得点を稼いでしまった方が何かと楽なので、短期間で効率よく合格を目指すのであれば、配点の高い分野を得意科目にしてしまった方が良いということです。
まずは、こちらの資料をご覧ください。
| \ | 管理 | 法令 | 測定 | 生体 | 合計 | ||
| 正誤問題 | ○ | 1問 | 4問 | 2問 | 4問 | 22問 | 55.0% |
| × | 4問 | 4問 | 2問 | 1問 | |||
| 組合せ問題 | 1問 | 1問 | 4問 | 5問 | 11問 | 27.5% | |
| 計算問題 | 2問 | --- | 2問 | --- | 4問 | 10.0% | |
| 穴埋め+組合せ問題 | 2問 | 1問 | --- | --- | 3問 | 7.5% | |
では、具体的にどのような形の問題が出題されているのか、具体例を挙げてみましょう。
問:エックス線に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (1)エックス線は、間接電離放射線である。 (2)制動エックス線は、軌道電子が、エネルギー準位の高い軌道から低い軌道へと転移するときに発生する。 (3)制動エックス線のエネルギー分布は、連統スペクトルを示す。 (4)特性エックス線は、ターゲットの元素に特有な波長をもつ。 (5)K系列の特性エックス線は、管電圧を上げると強度が増大するが、その波長は変わらない。 問:放射線検出器とそれに関係の深い事項との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。 (1)電離箱 ………………………… 飽和領域 (2)比例計数管 …………………… 窒息現象 (3)化学線量計 …………………… G値 (4)半導体検出器 ………………… 電子・正孔対 (5)シンチレーション検出器 …… 電子増倍 問:組織加重係数に関する次のAからDまでの記述のうち、正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 A:組織加重係数は、各臓器・組織の確率的影響に対する相対的な放射線感受性を表す係数である。 B:組織加重係数が最も大きい組織・臓器は、脳である。 C:組織加重係数は、どの組織・臓器においても1より小さい。 D:被ばくした組織・臓器の平均吸収線量に組織加重係数を乗ずることにより、等価線量を得ることができる。 (1)A,B (2)A,C (3)B,C (4)B,D (5)C,D 問:次の文中の[ ]に入れるAからCの語句又は数字の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。 「事業者は、エックス線装置を設置し、若しくは移転し、又はその主要構造部分を変更しようとするときは、所定の届書に、エックス線装置を用いる業務の概要等を記載した書面、[ A ]を示す図面及び放射線装置摘要書を添えて、当該工事の開始の日の[ B ]日前までに、所轄[ C ]提出しなければならない。」 (1)A=エックス線装置の構造 B=14 C=都道府県労働局長 (2)A=管理区域 B=14 C=労働基準監督署長 (3)A=エックス線装置の構造 B=14 C=労働基準監督署長 (4)A=管理区域 B=30 C=労働基準監督署長 (5)A=エックス線装置の構造 B=30 C=都道府県労働局長 |
エックス線に関する知識がない方にとっては、見慣れない語句が多く手が出ないという印象を受けたかもしれませんが、基本的な専門用語や知識を問う素直な問題が目立つ(法令や数字などは正確に暗記し、専門用語は意味を理解することが重要!)ため、化学を得意とする人や分析装置などを取扱う職場で働いているような方であれば、それほど難易度が高いと感じることはないはずです。
仮に化学が苦手であったり、まったく畑違いの職場で働いているという方でも、同試験は似たような問題が繰り返し出題される傾向が強いため、過去問を中心に勉強を進めれば、合格するだけの実力(得点)は必ず身に付きます。
ただ、エックス線作業主任者試験でやっかいなのが〝計算問題〟です。
問:波高値による管電圧が150kVのエックス線管から発生するエックス線の最短波長(nm)に最も近い値は、次のうちどれか。 (1)0.001 (2)0.008 (3)0.02 (4)0.08 (5)0.2 問:あるエネルギーのエックス線に対する鉄の質量滅弱係数が0.5㎠/gであるとき、このエックス線に対する鉄の1/10価層に最も近い厚さは次のうちどれか。ただし、鉄の密度は7.9g/㎤とし、loge2=0.69、loge5=1.61とする。 (1)3mm (2)4mm (3)5mm (4)6mm (5)7mm |
事実、同試験は計算問題の出題数が増えると合格率が下がりやすい傾向が見てとれるため、計算問題に関しては、意外と難易度の高い問題が出題されています。
そのため、すべての計算問題を捨て問題にしてしまうのはリスクが高く、あまりおススメできる手段ではありませんが、複雑な問題は後回しにして、過去に出題されている短時間で答えられるような計算問題くらいはしっかりとマスターし、後は運任せで本試験に臨むというのも一法です(ただし、近年はあまり単純な問題は出題されにくい・・・出ればラッキー!)。